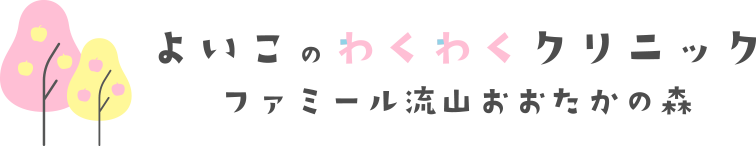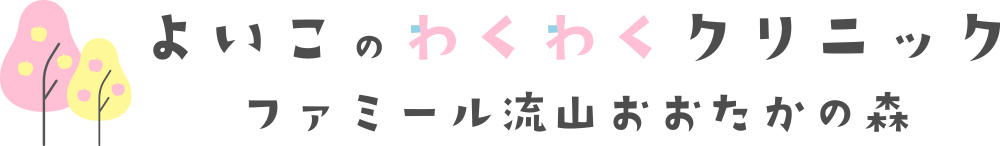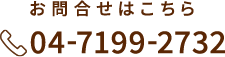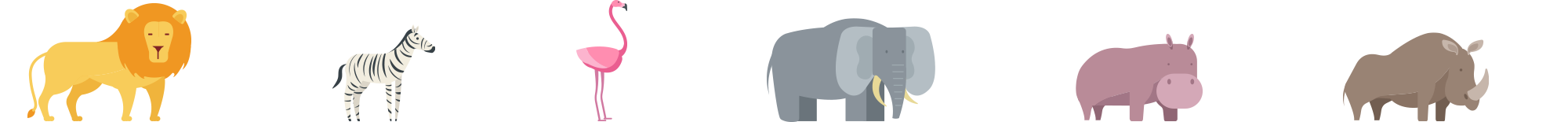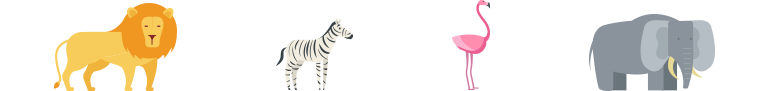ご予約についての注意点
発達相談や育児相談、夜尿症などのご相談は、お話をゆっくりお聞きする必要があります。予約枠の調整を行いますので、9:30から10:00の間に直接クリニックまでお電話ください。
子どもの夜尿症(おねしょ)
夜尿症(おねしょ)は、睡眠中に無意識のうちに尿が漏れてしまう状態で、年齢が5歳を過ぎても持続する場合に「夜尿症」と診断されます。成長段階や発達の個人差はあるものの、夜間の排尿コントロールが十分に確立していない場合や、遺伝的要因、心理的ストレス、睡眠の深さなどが原因とされています。治療には、生活習慣の改善や夜尿アラーム、必要に応じた薬物療法などが行われ、本人や保護者の不安解消と社会生活への適応をサポートします。安心して取り組める治療法も充実しており、専門医と連携したケアが重要です。
お子さまが夜にお漏らしをしても心配しないで
 お子さまが夜にお漏らしをしても、必ずしも深刻な病気ではありません。多くの場合、成長過程での発達の一環であり、夜間の排尿コントロールは徐々に身につくため、焦らずに見守ることが大切です。ご家族は過度に心配せず、適切なケアや環境整備を心がけることで、子どもの自信回復と正常な発達をサポートできます。
お子さまが夜にお漏らしをしても、必ずしも深刻な病気ではありません。多くの場合、成長過程での発達の一環であり、夜間の排尿コントロールは徐々に身につくため、焦らずに見守ることが大切です。ご家族は過度に心配せず、適切なケアや環境整備を心がけることで、子どもの自信回復と正常な発達をサポートできます。
小学校になっても夜尿症が治らない場合は小児科でご相談されることをお勧めいたします。
おねしょと夜尿症の違いは?
「おねしょ」は一般的に幼児期にみられる一過性の現象を指すのに対し、夜尿症は一定の年齢(通常5~7歳以降)を過ぎても夜間に尿が漏れる状態をいいます。前者は自然に改善する場合が多いのに対し、夜尿症は医療的な介入が必要なケースもあり、原因や治療法も異なります。
夜尿症の症状
夜尿症の主な症状は、睡眠中に無意識に尿が漏れることです。日中はトイレを我慢できるのに、夜間だけ排尿コントロールができず、起床時にベッドや衣服に尿の染みが認められる場合が多いです。また、頻繁なおねしょにより自己評価が低下したり、保護者の方が不安になったりするケースがあります。
夜尿症の原因
夜尿症の原因は、夜間の尿量、膀胱機能の未発達、遺伝的要因、ホルモン分泌の異常(抗利尿ホルモンの分泌不足)や深い睡眠状態、さらには心理的ストレスなどが複合的に影響しているとされています。特に家族歴がある場合や、情緒の不安定さがみられる場合は、夜間の尿意の認識が低下し、適切にトイレに起き上がることが困難になることが要因と考えられます。
| おねしょの回数 | |||
| 毎晩 | 半分程度/週 | 1・2回/週 | |
| 4歳~5歳 | 生活習慣の改善 | 経過観察 | 経過観察 |
| 6歳~7歳 | 治療が必要 | 生活習慣の改善または治療が必要 | 生活習慣の改善 |
| 8歳以上 | 治療が必要 | 治療が必要 | 治療が必要 |
※治療の方法や開始時期は人によって異なります。症状によっては、治療ではなく生活習慣の改善や、経過観察をご提案する場合もあります。
夜尿症の検査
夜尿症の検査はまず、詳細な問診や生活状況の把握から始まります。家族歴、夜間の尿量、夜尿の頻度、日中の排尿パターン、睡眠状態などを確認し、必要に応じて尿検査や血液検査、ホルモン検査を実施します。また、心身の発達状態や心理的ストレスの有無を評価し、原因の絞り込みと適切な治療方針を決めていきます。
夜尿症の治療
薬物療法
 夜尿症の治療において、薬物療法は抗利尿ホルモン製剤や、排尿コントロールを改善する薬剤が用いられます。抗利尿ホルモン(デスモプレシン)は、夜間の尿量を減少させる効果があり、適切な用量で服用することで症状の改善が期待されます。また、場合によっては排尿反射を改善する薬剤が併用されることもあります。副作用や効果を定期的に評価しながら進めていきます。
夜尿症の治療において、薬物療法は抗利尿ホルモン製剤や、排尿コントロールを改善する薬剤が用いられます。抗利尿ホルモン(デスモプレシン)は、夜間の尿量を減少させる効果があり、適切な用量で服用することで症状の改善が期待されます。また、場合によっては排尿反射を改善する薬剤が併用されることもあります。副作用や効果を定期的に評価しながら進めていきます。
アラーム療法
アラーム療法は、寝ている間に尿が出たことを感知すると音や振動で知らせる機器を用いる治療法で、子どもに排尿のタイミングを認識させる訓練装置です。使用することで、夜間にトイレに起き上がる習慣が徐々に身につき、排尿コントロールの改善を図ることができます。アラーム療法は、一定期間継続して使用することが必要ですが、多くの子どもで効果が認められており自然な排尿パターンの確立をサポートします。
生活習慣の改善
夜尿症の改善には、生活習慣の見直しも重要です。就寝前の水分摂取を控え、規則正しい生活リズムや十分な睡眠を確保することが推奨されます。また、日中にトイレに行く習慣をつけ、排尿習慣を改善することや、ストレスの軽減、適度な運動を心がけることも効果的です。家庭内での環境整備や、リラックスできる寝室作りなど、子どもの全体的な健康状態を向上させる工夫が、夜尿症の改善につながります。
- 十分な睡眠と規則正しい生活リズムを保ち、毎日同じ時間に就寝・起床することが重要です。
- 朝食と昼食はしっかりと摂り、夕食は就寝の3時間前までに済ませるようにしましょう。
- 寝る直前の水分摂取は控え、夕食後から就寝までの間は、約コップ1杯程度に留めると良いです。
- 塩分の過剰摂取は喉の渇きを招き、余計な水分摂取につながるため注意が必要です。
- 便秘にならないよう、食物繊維が豊富な食事を心がけ、腸内に便がたまりすぎないようにしましょう。
- 寝る前には必ずトイレに行って、夜間の排尿負担を軽減します。
- 睡眠時の寒さや寝冷えに注意し、体が冷えないように工夫することで、尿の過剰生成と膀胱の収縮を防ぎます。
- 夜中に無理にトイレに起こさなくても大丈夫です。
小学生のおねしょはご相談ください
小学生になってもおねしょが続く場合は、単なる発達の遅れだけでなく、心身の問題や内分泌の異常が関与している可能性があります。学校生活に支障が出る前に、専門医に相談し、適切な検査や治療を受けることが重要です。おねしょの原因は個々に異なるため、早期の診断と対策が将来の発達や自信回復につながります。
夜尿症(おねしょ)のよくある質問
子どものおねしょはどうすれば治せますか?
生活習慣の改善、アラーム療法、薬物療法など、個々の症状に合わせた多角的なアプローチが効果的です。医師と相談の上、適切な治療計画を立てることが重要です。
子どもがおねしょをするのはどうしてですか?
排尿コントロールの未発達、遺伝的要因、ホルモン分泌の乱れ、深い睡眠状態、心理的ストレスなどが原因として考えられます。
子どものおねしょの原因はストレスが関係していますか?
はい。家庭や学校での心理的ストレスが排尿反射に影響を与え、夜間のおねしょを引き起こす場合があります。
おねしょは何歳から病気と診断されますか?
一般的には5歳以降で夜間の排尿が持続する場合、夜尿症として診断されることが多いです。
夜尿症は放置していたら自然に治りますか?
多くの場合、成長とともに自然治癒することもありますが、長期にわたる場合は治療が必要なケースもあります。
5歳になってもおむつが中々取れない原因は何ですか?
個々の発達や、深い睡眠状態、排尿の自覚の遅れなどが影響し、家庭環境や生活習慣も関係しています。
夜におむつを外す年齢はいつぐらいがいいですか?
一般的には就寝前のトイレ習慣が確立され、夜中におむつに尿をしていないなどの条件が揃う4~5歳頃が目安です。個人差があるため、小児科医や保育士など、身近な専門家に相談してみてください。
夜尿症と発達障害は関係していますか?
発達障害のある子どもは排尿の自覚やコントロールが難しい場合もあり、夜尿症がみられることがあります。詳しくは専門医の評価が必要です。