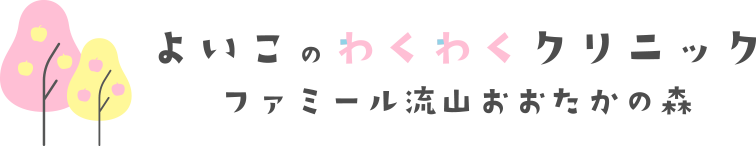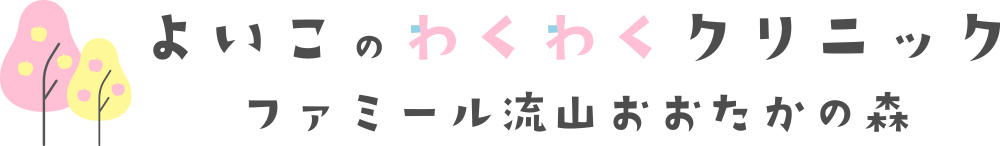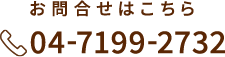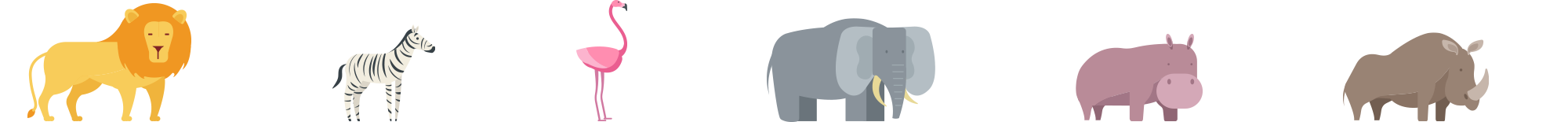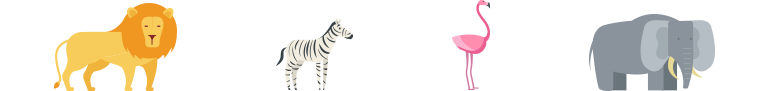子どもの風邪(風邪症候群)

風邪とは正式には風邪症候群と言い、発熱やくしゃみ、鼻水、鼻づまり、咳、のどの痛みなどの症状を引き起こす病気の総称です。主にウイルスなどの異物が、鼻やのどの粘膜に感染して炎症を起こすことで発症します。
原因のほとんどがウイルス感染のため、特効薬はなく、症状を抑えるための対症療法を行いながらウイルスが体外に排出されるのを待ちます。
子どもの風邪の症状
子どもの風邪の原因
風邪の原因の80〜90%はウイルス感染で、残りは細菌やマイコプラズマなどによる感染となります。風邪の原因となるウイルスは200種類以上あると言われており、ウイルスによっては一般的な風邪の症状に加えて、結膜炎や下痢、嘔吐、皮疹などを引き起こすこともあります。一度感染したウイルスに対しては抗体ができますが、他のウイルスに感染すると再び風邪を発症します。大人は、過去に多くのウイルス感染経験があるために風邪への抵抗力が高いですが、子どもはウイルス感染の経験が浅いために風邪を引きやすい傾向があります。したがって、子どもが何度も風邪を引くのは、体内に様々なウイルスに対する抗体を獲得し、免疫力を高めるための過程とも言えます。
子どもに多いウイルスによる風邪
ライノウイルス
ライノウイルスは、風邪ウイルスの中でも最も多いウイルスで、全体の30~40%を占めます。特に春と秋に多く見られ、鼻風邪を引き起こす特徴があります。
コロナウイルス
コロナウイルスは、風邪ウイルスの中でもライノウイルスの次に多いウイルスです。主に冬場に流行し、鼻やのどに比較的軽度な風邪症状を引き起こす特徴があります。
ヘルパンギーナ
ヘルパンギーナとは、コクサッキーウイルスが原因で発症し、発熱やのどの痛みの風邪症状の他、水疱などを引き起こす病気です。一般的に乳児や幼児を中心に流行し、夏場に多いことから代表的な夏風邪となっています。
手足口病
手足口病もヘルパンギーナと同様、コクサッキーウイルスが原因で発症する病気です。乳児や幼児を中心に流行することや夏場に多く見られることもヘルパンギーナと共通していますが、手足口病の場合は、口や手足に特徴的な発疹が現れます。
アデノウイルス
アデノウイルスは、一般的にプール熱の原因と言われているウイルスです。冬から夏にかけて感染が拡大し、感染すると咽頭炎や気管支炎といった風邪症状の他、結膜炎などの症状も引き起こす特徴があります。
RSウイルス
RSウイルスは、乳児や幼児が感染すると気管支炎や肺炎などを引き起こすウイルスです。1年を通して感染する恐れがありますが、特に冬場に多く見られます。
ヒトメタニューモウイルス
ヒトメタニューモウイルスは、RSウイルスと類似した症状を引き起こすウイルスです。1年を通して感染する恐れがありますが、特に3〜6月頃に多く見られます。
パラインフルエンザウイルス
パラインフルエンザウイルスは、感染すると鼻やのどに風邪症状を引き起こすウイルスで、秋に流行するタイプと春から夏にかけて流行するタイプの2種類があります。特に、乳児や幼児が感染すると重症化する恐れがあるため、注意が必要です。なお、インフルエンザという名前が入っていますが、インフルエンザとは別の病気となります。
エンテロウイルス
エンテロウイルスは主に夏場に流行するウイルスで、感染すると鼻やのどに風邪症状を引き起こす他、下痢を伴うこともあります。
インフルエンザ
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することで発熱や鼻水、鼻づまり、咳、のどの痛みなどの風邪症状を引き起こす代表的な病気です。例年冬場に流行し、感染力が高いことから学校等で集団感染を起こすこともあります。また、幼児や高齢者が感染すると合併症を引き起こして死亡する場合もあり、注意が必要です。
子どもの風邪の治療
風邪の主な原因はウイルスであることが多いため、治療は症状を抑えるための対症療法が中心となります。一般的な風邪薬には発熱や鼻・咳症状を抑えるものが多いですが、発熱やくしゃみ、咳などの症状は体内のウイルスを排出するための防衛反応であるため、あまり過度に飲み過ぎない方が良いとも言われています。
また、子どもが風邪を引いて鼻水を出していたら、こまめに拭き取るようにしましょう。放置すると、鼻に細菌やウイルスが増殖して中耳炎を併発する恐れもあります。また、小さな子どもは自分で鼻をかむことができないため、鼻が詰まってしまった場合には吸引器を使用したり、小児科を受診して吸引すると良いでしょう。
子どもが風邪をひいた時の対応
安静にして過ごす
症状を改善するためには、安静状態を保つことが大切です。発熱がなく元気な場合は、無理に休ませる必要はありませんが、外出したり激しい運動をしたりすると再発する恐れもあるため、注意しましょう。
こまめに水分補給をする
 風邪を引いて発熱を起こすと大量の汗をかくため、こまめに水分補給を行って脱水症状を防ぎましょう。水分の取り方には特に制約はありませんが、柑橘系のジュースや炭酸飲料はのどを刺激して咳症状を助長してしまうため、避けるようにしましょう。
風邪を引いて発熱を起こすと大量の汗をかくため、こまめに水分補給を行って脱水症状を防ぎましょう。水分の取り方には特に制約はありませんが、柑橘系のジュースや炭酸飲料はのどを刺激して咳症状を助長してしまうため、避けるようにしましょう。
食欲がないときは無理に食べさせない
風邪を引くと胃腸の機能が低下して一時的に食欲が減退しますが、十分な水分補給を行っていれば無理に食べさせる必要はありません。食事のタイミングは、子どもが食べたがる時間に適宜合わせるようにしましょう。ただし、お菓子やラーメンなどの脂質を多く含むものや、さつまいもやかぼちゃなど食物繊維を多く含むものは胃腸の負担を増大させるため、避けるようにしましょう。
お風呂は無理に入らせない
 お風呂は多くの体力を使うため、風邪を引いて体力が低下している時は避けるようにしましょう。ただし、からだの汚れが蓄積すると、細菌やウイルスが繁殖して他の病気を併発する恐れがあるため、お風呂に入れない場合には、固く絞った蒸しタオルなどを使い、からだを拭いてあげましょう。
お風呂は多くの体力を使うため、風邪を引いて体力が低下している時は避けるようにしましょう。ただし、からだの汚れが蓄積すると、細菌やウイルスが繁殖して他の病気を併発する恐れがあるため、お風呂に入れない場合には、固く絞った蒸しタオルなどを使い、からだを拭いてあげましょう。
また、発熱がなく元気な場合はお風呂に入っても問題ありませんが、長時間浸かると体力を消耗するため、短時間で済ませるかシャワーだけにするなど工夫をしましょう。