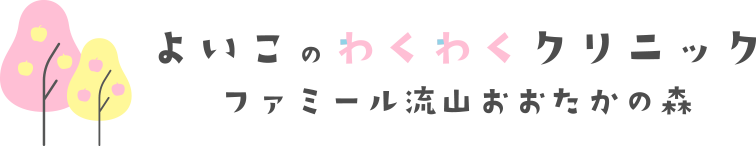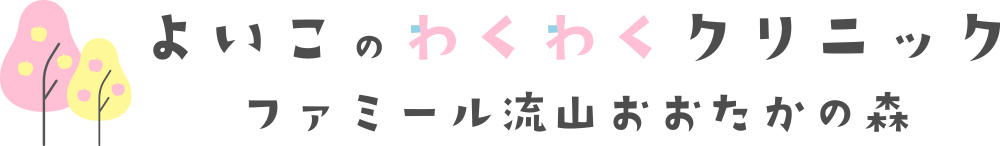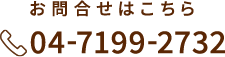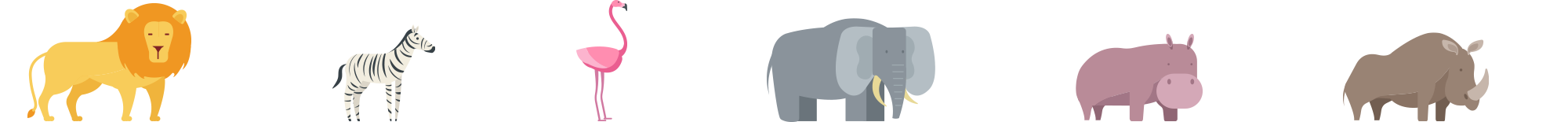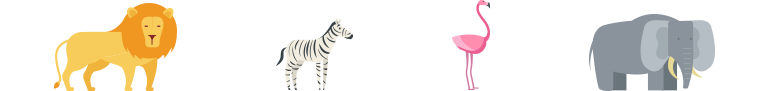子どもの皮膚の病気
 子どもの皮膚は大人に比べて薄いため、様々なトラブルを引き起こします。子どもは大人のように自身のからだのトラブルを上手に訴えることが難しいため、ご家族さまをはじめとした周囲の方々が、常に気を配って状態を把握してあげることが大切です。
子どもの皮膚は大人に比べて薄いため、様々なトラブルを引き起こします。子どもは大人のように自身のからだのトラブルを上手に訴えることが難しいため、ご家族さまをはじめとした周囲の方々が、常に気を配って状態を把握してあげることが大切です。
子どもが乾燥やアレルゲンなどによってかゆみといった症状を引き起こした際には、スキンケアおよび外用剤による治療が有効です。当院では、様々な皮膚トラブルに効果的な外用剤の使用法についてアドバイスしております。
お子さまの皮膚に気になる症状が現れている場合は、ぜひお気軽に当院までご相談ください。
子どもの皮膚でよくある病気
- みずぼうそう(水痘)
- 麻疹(はしか)
- 風疹(三日はしか)
- 突発性発疹
- 伝染性紅斑(りんご病)
- 手足口病
- おむつかぶれ
- 乳児湿疹
- 乳児脂漏性皮膚炎(乳児脂漏性湿疹)
- 皮脂欠乏症・皮脂欠乏性湿疹
- じんましん(蕁麻疹)
- あせも
- 虫刺され
- いぼ
- 水いぼ
- にきび
- アトピー性皮膚炎
- とびひ(伝染性膿痂疹)
- 新生児ざ瘡
- 頭じらみ
- 乳児血管腫・苺状血管腫
など
ウイルス感染症
皮膚に発疹ができる主なウイルス感染症は以下となります。
水痘(水ぼうそう)
水痘とは一般的に水ぼうそうと呼ばれている病気で、水痘・帯状疱疹ウイルスに感染することで発症する感染症です。感染後約 2 週間の潜伏期間を経たのち、37~38℃台の発熱とともに丘疹という小さく盛り上がった赤い発疹が全身に現れるようになります。発疹の発生とともにかゆみを伴いますが、1 週間程すると水疱はかさぶたに変化してかゆみは治まっていきます。すべての水痘がかさぶたに変化すれば、登園や登校が可能となります。
主な治療法は、塗り薬によってかゆみを抑える対症療法を行いつつ、抗ウイルス薬を使用して症状の改善や再発を予防します。
麻疹(はしか)
麻疹とは麻疹ウイルスに感染することで発症する感染症です。感染後の潜伏期間は約2週間で、その後様々な症状が現れます。
主な症状は、38~39℃の発熱やのどの痛み、咳、鼻水に加え、皮疹や口内にコプリック斑という白いぶつぶつができるなどが挙げられます。皮疹は最初顔や首に現れ、その後全身に広がり、しばらくすると色素沈着を残して自然に消失していきます。
治療では、症状を緩和するための対症療法を中心に行います。なお、麻疹はワクチン接種によって予防が可能なため、定期的に予防接種を行うようにしましょう。
風疹(三日はしか)
風疹とは風疹ウイルスに感染することで発症する感染症で、麻疹と類似した症状が3~5日間現れることから「三日はしか」とも呼ばれます。感染後の潜伏期間は2~3週間で、その後様々な症状が現れます。
主な症状は、38~39℃の発熱や小さく盛り上がった赤い発疹(小丘疹)、リンパ節の腫れなどが挙げられますが、風疹の発疹は麻疹と異なり色素沈着せずに消失していく特徴があります。
また、妊娠初期の妊婦が風疹に感染すると、胎盤を通じてウイルスが胎児に移行し先天性風疹症候群を発症する恐れがあるため、特に注意が必要です。先天性風疹症候群の主な症状は、難聴や心疾患、先天性白内障などになります。
突発性発疹
突発性発疹とは、ヒトヘルペスウイルス6型・7型に感染することで発症する感染症です。まず39℃近くの発熱が3~4日程続き、発熱が治まった頃に発疹が現れます。発疹は痛みやかゆみを伴わず、数日程で自然消失します。
発熱しても元気でいることが多いですが、発疹が現れると不機嫌な状態が続く場合があります。また、必ずとは限りませんが、子どもの場合は軟便や下痢症状を伴うこともあります。主な治療は、解熱剤などを使用して症状の緩和を図り、その後経過観察します。
伝染性紅斑(りんご病)
伝染性紅斑とは一般的にりんご病とも呼ばれている病気で、ヒトパルボウイルスB19に感染することで発症する感染症です。感染後の潜伏期間は約2週間で、その後頬に紅斑が生じたり、四肢に網目状の発疹が拡大したりするなどの症状が現れます。発疹は1週間程度で色素沈着せずに自然消失します。その他では、発疹が発生する7~10日程前に微熱や感冒などの症状が現れたり、人によっては関節痛を起こしたりします。
なお、ヒトパルボウイルスB19は、紅斑が発生した頃には体外に排出されているため、その後は登園・登校することが可能です。
主な治療としては、抗ヒスタミン剤を使用して症状の緩和を図ります。
妊娠初期の妊婦さんにこのウイルスが感染すると、胎児に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
手足口病
手足口病とはコクサッキーウイルスA16やエンテロウイルス71などに感染することで発症する感染症で、手や足、口腔内に小さな水疱が発生することからこのような名称が付けられています。
発疹は3~5日間の潜伏期間を経たのちに発生し、その後1週間~10日程で色素沈着せずに自然消失します。ただし、口腔内の小さな水疱による痛みによって一時的に食欲不振に陥ることがあるため、この間は適度の水分補給をしながら脱水症状を予防することが大切です。また、手足口病は症状が改善した後も2~4週間は便にウイルスが残留している可能性があるため、排便後にはこまめに手洗いを行うようにしましょう。
おむつかぶれ
 おむつかぶれとは、おむつと接触する皮膚が尿や便に含まれるアンモニアによって刺激を受け、ただれたりブツブツができたりする状態です。主な症状は、接触部の痛みやかゆみなどですが、放置するとカンジダ皮膚炎などを合併する恐れもあるため、注意が必要です。主な治療は、ぬるいお湯で患部を優しく洗ったのち、軟膏やワセリンなどを使用した薬物療法となります。また、重度の場合にはステロイド外用薬の使用を検討しますが、カンジダ皮膚炎を起こしている場合には症状を悪化させる恐れがあるため、使用するかどうかは医師の指示に従うようにしましょう。
おむつかぶれとは、おむつと接触する皮膚が尿や便に含まれるアンモニアによって刺激を受け、ただれたりブツブツができたりする状態です。主な症状は、接触部の痛みやかゆみなどですが、放置するとカンジダ皮膚炎などを合併する恐れもあるため、注意が必要です。主な治療は、ぬるいお湯で患部を優しく洗ったのち、軟膏やワセリンなどを使用した薬物療法となります。また、重度の場合にはステロイド外用薬の使用を検討しますが、カンジダ皮膚炎を起こしている場合には症状を悪化させる恐れがあるため、使用するかどうかは医師の指示に従うようにしましょう。
乳児湿疹
乳児湿疹とは、乳児の段階に皮膚に起きる湿疹の総称です。主な症状には、口・頬を中心とした顔面や頭部、首、手足、足首などに赤い乾燥したぶつぶつができることが挙げられます。一般的に湿疹は、皮脂分泌が多い部位や汗で蒸れやすい部位に多くできる特徴があります。ほとんどの場合は、しばらくすると自然消失しますが、中には長期間継続したり、赤み・かゆみ症状が激しくなったりすることもあります。その場合は、アトピー性皮膚炎の疑いがあります。炎症が強い場合にはステロイド外用薬などによる治療も検討しますので、当院までご相談ください。
乳児脂漏性皮膚炎(乳児脂漏性湿疹)
乳児脂漏性皮膚炎とは、主に皮脂を分泌する皮脂腺が多く集中している部位に発生する、
黄色っぽいかさぶたのような湿疹ができる状態のことを指します。皮脂腺はおでこや頭部、首、わき、股に多く集中しているため、これらの部位に発生する場合が多く見られます。乳児脂漏性皮膚炎の原因は、まだはっきりとは明らかになってはいませんが、マラセチアという細菌に感染することで引き起こされるのではないかと考えられています。
多くの場合は、生後3か月頃までに自然消失しますが、中には炎症が長期間継続することもあります。その場合は、アトピー性皮膚炎の疑いがあります。炎症が強い場合には乳児湿疹と同様にステロイド外用薬などによる治療も検討しますので、当院までご相談ください。
皮脂欠乏症・皮脂欠乏性湿疹
皮脂欠乏症とは、皮脂分泌が不足することで皮膚表面がカサカサに乾燥した状態です。乾燥が激しいと白い粉を吹くこともあり、また更に進行すると皮膚表面に湿疹を伴う皮脂欠乏性湿疹を発症することもあります。一般的に皮脂分泌量は新生児の段階で増加し、生後6か月を超えると徐々に減少していくため、この頃に皮脂欠乏症や皮脂欠乏性湿疹を発症する場合が多く見られます。
対応としては、加湿器などで部屋の湿度を調整し、ヘパリン類似物質などの保湿剤を使用して皮膚表面の水分を補ってあげることが効果的です。ただし、これら対策を行ってもかゆみを伴う湿疹が2か月以上継続している場合は、アトピー性皮膚炎などの他の病気の可能性も考えられるため、できるだけ早く当院までご相談ください。
じんましん(蕁麻疹)
蕁麻疹とは、何らかの原因によって強いかゆみを伴う赤く盛り上がった発疹ができる病気です。蕁麻疹には様々な種類があり、軽微な刺激によって発生する特発性蕁麻疹や特定の刺激によって発生する刺激誘発型蕁麻疹、蕁麻疹関連疾患、血管性浮腫などに分類されます。多くの場合は、数十分~数時間で自然消失しますが、稀に1か月以上症状が継続することもあります。
発疹がからだの一部に現れている場合は、患部を冷やすことで改善することが多いですが、それでも改善しない場合や発疹が全身に現れている場合には、抗ヒスタミン内服薬を使用した薬物療法を検討します。
虫刺され
虫刺されは日常的に起きる症状の一つですが、子どもの場合は刺されてから数日後に症状が現れたり、大人に比べて腫れ症状が強かったりする傾向があります。虫刺されによる痛みやかゆみは、主に刺された際の刺激と虫の分泌液によるアレルギー反応によって引き起こされます。
また、症状は刺された虫の種類や刺された場所、お子さまの体質などによって異なるため、治療を行う際には原因を特定した上で、症状に応じた治療法を検討します。
いぼ
いぼは、正式には疣贅(ゆうぜい)と言われる病気で、皮膚の上に隆起したできものの総称です。いぼには、加齢が原因で発生するものやウイルス感染が原因で発生するものなどの様々な種類があり、治療を行う際には原因を特定した上で、最適な治療法を検討することが必要となります。
水いぼ
水いぼとは、皮膚の表面に数㎜程度の水泡のような小さなできものが多数できる病気です。水いぼは、正式には伝染性軟属腫と言われ、主にポックスウイルスへの感染が原因とされています。我々の皮膚には、通常ではウイルスの増殖を防ぐためのバリア機能が備わっていますが、病気等の理由によってバリア機能が低下したり、もともと皮膚が未発達な子どもには水いぼが発生しやい傾向があります。
ほとんどの場合は数カ月から1年程度で自然治癒します。しかし、無意識に触ったり、衣服でこすれて破けると、いぼの中にいるウイルスが別の部位の肌について新しい水いぼができるため注意が必要です。症状が長期間継続している場合やかゆみが出た場合、基礎疾患を持っている場合には、ヨクイニンという漢方を内服することで、個人差はありますが皮膚の免疫力を上げること が期待されます。さらに、水いぼをピンセットで除去したり、液体窒素を使用して除去したり、自費診療の軟膏を使用するなどの治療を検討することもありますが、当院では実施していないので皮膚科にご相談ください。
にきび(尋常性ざ瘡)
にきびとは正式には尋常性ざ瘡と言い、毛穴に詰まった皮脂にアクネ菌が繁殖することで炎症を引き起こす病気です。アクネ菌は常在菌のため、本来は皮膚上に存在していても特に問題はありませんが、異常増殖すると皮膚が炎症を起こしてにきびが発生します。思春期ににきびが多くなるのは、ホルモンバランスが乱れることで多くの皮脂分泌が起きるためです。
主な治療は、炎症を抑えるための抗菌薬や毛穴に皮脂が詰まるのを抑えるためのお薬を使用することになります。
あせも
あせもとは、発汗量の多い皮膚上に小さなぶつぶつや水ぶくれが発生した状態です。一般的に発汗量が増加する夏場に多く見られる他、大人よりも子どもに多く見られる傾向があります。
多くの場合は無症状で、しばらく放置すると自然消失しますが、中にはかゆみを伴うこともあります。かゆみ症状が激しい場合には、抗ヒスタミン内服薬やステロイド外用薬を使用します。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎とは、何らかの原因によって皮膚のバリア機能が低下し、皮膚の乾燥や湿疹、激しいかゆみなどの症状を引き起こすアレルギー疾患の一つです。湿疹が発生する場所は年齢によって異なり、一般的に乳幼児期は顔や頭部にできやすい傾向があります。また、幼児期~学童期では肘や膝などの関節部内側に、思春期には顔を中心とした上半身に赤みを伴った湿疹が多く発生するようになります。なお、アトピー性皮膚炎は症状の悪化と改善を繰り返す傾向もあります。
主な治療は、保湿能力の高いスキンケアによって皮膚の乾燥を防ぐこと、症状の程度によってステロイド外用薬や免疫抑制剤を使用することになります。
伝染性膿痂疹(とびひ)
伝染性膿痂疹とは、一般的にとびひと呼ばれている病気で、黄色ブドウ球菌や化膿性連鎖球菌に感染することで皮膚トラブルを引き起こす感染症です。感染すると水ぶくれのような湿疹が全身に広がり、皮膚が破れて浸出液が出たり、黄色いかさぶたを形成したりするなどの症状を引き起こします。また、かゆみを我慢できずに掻きむしってしまうと、感染範囲が拡大する恐れがあるため、注意が必要です。
主な治療は、症状が軽度であれば抗菌効果のある外用薬を使用し、重度の場合には抗生物質や抗ヒスタミン剤の内服薬による薬物療法を行います。
新生児ざ瘡
新生児ざ瘡とは、一般的には赤ちゃんにきびと言われているもので、皮脂腺が活発になる生後2週間程の新生児に発生する発疹のことを指します。ほとんどの場合は、数か月程経過すると自然消失します。主な原因は、通常のにきびと同様に常在菌が関与していると考えられていますが、まだはっきりとした原因は明らかになってはいません。
新生児の肌に優しいスキンケアを使用し、毎日皮膚表面を丁寧に洗浄してあげることが大切です。
頭じらみ
頭じらみとは、髪の毛の中に虫の卵が付着することでかゆみなどの症状を引き起こす病気です。夏場の外出時に多く見られ、放置すると卵が孵化して幼虫が活動するようになります。また、家族内で一人発症者が出ると、家族間で感染が拡大する恐れもあります。
主な対処法はこまめな髪の毛の洗浄で、特にスミスリンというシラミに効果的な成分を含有した市販のシャンプーを使用すると2週間程で改善します。
乳児血管腫・苺状血管腫
乳児血管腫・苺状血管腫とは真っ赤なあざが発生する病気で、一般的に生後1か月頃の赤ちゃんに多く見られます。主な原因は未熟な毛細血管の異常増殖で、生後6か月ころまで増大し、ほとんどの場合は5~7歳頃には自然消失しますが、中にはその後も皮膚のたるみや色素沈着などの痕が残ることもあります。
乳児血管腫・苺状血管腫は良性腫瘍のため、放置しても特に問題はありませんが、早期に介入しβ遮断薬シロップの使用やレーザー手術などによって改善することが可能です。また、目や耳、気道などに発疹が発生すると身体機能の悪影響を及ぼす恐れがあるため、その際にも治療を検討します。