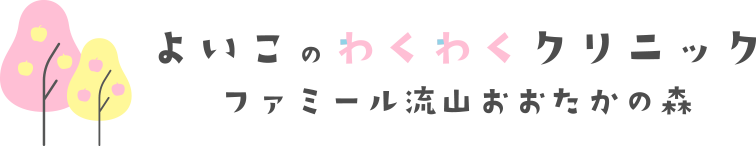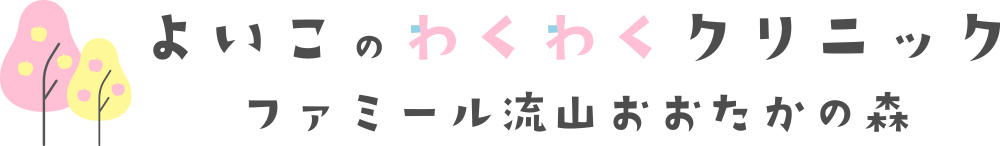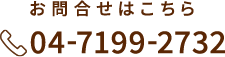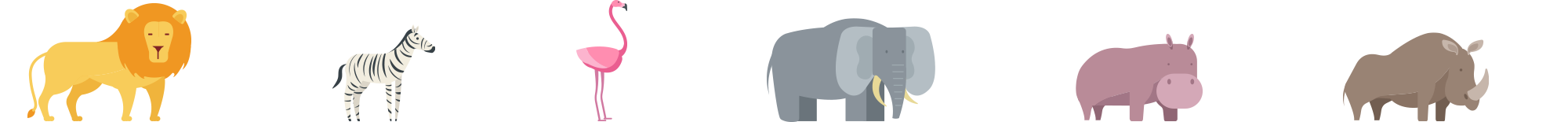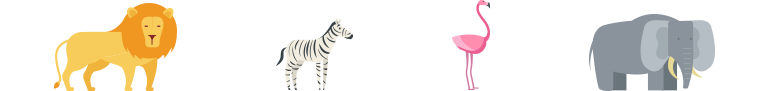- 子どもの発達・行動・こころの相談
- お子さまの発達・行動でお悩みなことはありますか?
- 神経発達症(発達障害)とは
- 二次障害・精神疾患
- 子どもの発達・行動・こころの症状に対して診断をしてもらうべき?
- 不登校・引きこもりでお悩みの方もご相談ください
ご予約についての注意点
発達相談や育児相談、夜尿症などのご相談は、お話をゆっくりお聞きする必要があります。予約枠の調整を行いますので、9:30から10:00の間に直接クリニックまでお電話ください。
なお、当院での発達相談は、患者さまから詳しくお話を聞かせていただいた上で、療育の必要性に関しての判断を行っております。診断および療育を行うことはできないため、すでに他施設で定期フォローを行われている患者さまはご遠慮いただいております。予めご了承ください。
子どもの発達・行動・こころの相談
 自分の子どもが同世代に比べて発達が遅い、気になる言動が多い、精神的に不安定であるなどの症状を起こしている場合は、何らかの病気が関与している可能性があるため、できるだけ早く医療機関を受診して検査を受けるようにしましょう。
自分の子どもが同世代に比べて発達が遅い、気になる言動が多い、精神的に不安定であるなどの症状を起こしている場合は、何らかの病気が関与している可能性があるため、できるだけ早く医療機関を受診して検査を受けるようにしましょう。
一方で、子どもの発達のスピードには個人差があるため、検査をしても特にからだの異常が見つからないこともあります。近年では様々なメディアから多くの情報を取得できることから、自分の子どもに対して必要以上に心配したり、子どもができないことを無理に強要したりしてしまうような間違った教育をされている親御さまも多く見られます。
当院では、子どもの発達や行動、精神状態についてお悩みの親御さまに対して、相談を承っております。子どもに気になる症状が現れている場合や、周囲に相談できる方がいない場合には、自己判断で行動したり、一人で抱え込んだりせずに当院までお気軽にご相談ください。心理検査を含めた専門的な診断や治療の必要性、療育の必要性を判断し専門病院に紹介させていただきます。
お子さまの発達・行動でお悩みなことはありますか?
以下は親御さまから寄せられるご相談の中で、特に多いお子さまの行動例です。ただし、子どもは年齢によって行動が変化するため、自分の子どもが以下に該当するからと言って直ちに対処が必要というわけではありません。このまま放置しても良いのか、やめさせるべきなのか分からない場合は、ぜひお気軽に当院までご相談ください。
- あまり喋らない
- あまり笑わない
- 目を合わせない
- まばたきの回数が多い
- こちらの言葉や指示を理解できない
- 自己主張が強い
- 歩く、座るなどの行動ができない
- よくかんしゃくを起こす
- よく汚い言葉を発する
- イライラしていることが多い
- よく顔をしかめる
- 落ち着きがない
- 集中力が持続せず注意力が散漫である
- 生活習慣や社会的ルールが身につかない
- 感情の起伏が激しく、突発的・衝動的な行動が多い
- 忘れ物・ものを無くすことが多い
- 音や匂いなどの刺激に対して敏感である
- 寝付きが悪い、夜泣きが多い、夜中に何度も目覚めてしまう、寝起きが悪い
- 周囲に馴染めず一人でいることが多い
- 運動が得意でない
- 他人に対して暴力的である
- 登園・登校したがらない
- 頭痛や腹痛などからだの痛みをよく訴える
- 立ちくらみが多い
- 過食・食欲不振が多い
- 何事にも興味や意欲を示さない
など
神経発達症(発達障害)とは
神経発達症とは一般的に発達障害と言われているもので、何らかの原因によって脳の発達速度や発達プロセスが同世代と異なることで、特徴的な認知や行動を示す状態です。アメリカ精神医学会によると、神経発達症は知的発達症、自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、限局性学習症、発達性協調運動症などに分類されています。
神経発達症を引き起こす原因は、まだはっきりとは明らかになってはいませんが、てんかんや早産、脳の障害などによる何らかの脳神経疾患などが関与していると考えられています。親御さまにとって大切なことは、神経発達症に関する正しい知識や、お子さま一人ひとりに合った効果的な育児法・教育法を身につけることになります。何かお困りごとやお悩みごとがございましたら、一人で抱え込まずにお気軽に当院までご相談ください。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症(ASD)とは、他人とは異なるこだわりを持っていたり、他者とのコミュニケーションが苦手だったりなどの特徴を持つ神経発達症の一つです。主な特徴として、相手の気持ちが理解できない、他者とは異なる部分に興味や執着を示す、個性的な遊び方をする、他者と目を合わせようとしない、感情や表情の変化があまりない、発語が遅い、偏食が強いなどが挙げられます。
注意欠如多動症(ADHD)
注意欠如多動症(DHD)とは、同世代の平均的な子どもに対して注意力や行動に固有の特徴を示す神経発達症の一つです。主な症状として、注意力が散漫、集中力が持続せずに落ち着きがない、常に動いている、衝動的に行動したり暴力を振るったりするなどが挙げられます。
注意欠如多動症と診断された際には薬物療法による治療を検討します。なお、処方は登録医でしか処方できないものもあり専門病院で判断していただきます。
限局性学習症(SLD)
限局性学習症(SLD)とは、知的発達には問題がないにもかかわらず、読み書きや計算などの特定の機能に障害が起きる神経発達症の一つで発達性読み書き障害ともいいます。読み書きが苦手で、努力しても改善されない場合には限局性学習症(SLD)の疑いがあります。
発達性協調運動症
発達性協調運動症とは、身体的異常が見当たらないにもかかわらず、同世代の子どもに比べて協調運動が苦手な状態です。協調運動とは、文字を書く、自転車に乗るなど、からだの複数の部位を繋げて行う運動のことを指します。視覚や知覚、触覚、自分の体の位置や動き、力の入れ具合を感じる感覚などの情報を統合し、目的に合わせて対応、修正していく一連の脳機能の障害とされています。
発達性協調運動症は、自閉スペクトラム症や注意欠如多動症、限局性学習症の発達障害を持つ子どもの数十%に認められます。明らかな遅れではないが乳児期から運動発達がゆっくりで、その後よく転ぶ、走るのが遅い、姿勢が悪いといった運動の苦手さや身体バランスの悪さが目立ち始めます。さらに幼児期後期から小学校入学後に日常動作がうまくできず時間がかかり、学校生活にも支障をきたすようになります。
発達性協調運動症と診断された場合は、子ども一人ひとりに合った運動プログラムを作成し、楽しく訓練してもらうことで運動に対する自信を付けさせていくことが大切です。
発達性協調運動症の主な症状は以下になります。
- 上手にハイハイができない
- つまずいた時に顔から転んでしまう
- 座っている時にからだがそわそわする
- 姿勢が保つことができない
- 上手に字が書けない
- 筆圧が弱い
- 上手に箸が使えない
- 靴ひもが結べない
- ボタンをはめることができない
- キャッチボールができない
- 縄跳びができない
- 自転車に乗れない
二次障害・精神疾患
子どもに発達特性が認められると、次第に同世代の友達との関係性に問題が生じたり、社会に対する不安感・違和感を覚えたりするようになります。このような状態が継続すると徐々に精神面が不安定になり、不登校や引きこもり、うつ症状、不安障害などの二次障害を引き起こす恐れもあります。
親御さまの立場としては、子どもが二次障害を引き起こした場合には無理に頑張らせようとせず、今まで以上に子どもの状況を理解し、お子さまと上手に接しながら生活環境を整えていくことが大切です。
お子さまの二次障害や精神疾患に関してお悩みごとがございましたら、一度当院までお気軽にご相談ください。
子どもの発達・行動・こころの症状に対して診断をしてもらうべき?
子どもの神経発達症には明確な診断基準がないため、診察する医師によっても多少の見解の差が生じます。例えば、お子さまが学校の勉強についていけなくても知的障害と診断されない場合や、落ち着きがなくてもその子どもの個性と判断される場合もあります。
親御さまの立場からすると、明確な診断名がつけば社会福祉面や教育面で様々な支援を受けることができるのに、診断名がつかないことに疑問や不安を感じることもあるでしょう。しかし、子どもの発達ペースには個人差があるため、お子さま一人ひとりの特性に合った教育や接し方を実践することが大切です。このような取り組みによって、その後お子さまが神経発達症と診断されなくなることも多く見られます。
不登校・引きこもりでお悩みの方もご相談ください
 文部科学省では、「病気や経済的事情などのやむを得ない理由以外によって年間で 30 日以上、学校に行かない、または行きたくても行けない状態」を不登校と定義しています。ただし、これはあくまで一つの基準であって、この条件を満たしていない場合でも、子どもの精神状態に障害が起きていることもあります。
文部科学省では、「病気や経済的事情などのやむを得ない理由以外によって年間で 30 日以上、学校に行かない、または行きたくても行けない状態」を不登校と定義しています。ただし、これはあくまで一つの基準であって、この条件を満たしていない場合でも、子どもの精神状態に障害が起きていることもあります。
子どもが不登校になる原因や背景には、様々な要因が複雑に絡んでいることが多く見られます。親御さまの立場としては、まずはお子さまと向き合い、お子さまの置かれている状況や不登校へと至った経緯を十分に理解した上で、一人ひとりに合った対応を講じていくことが大切です。特に、不登校の背景には発達特性や起立性調節障害などが潜んでいることもあるため、決して無理に再登校させようとしないことが重要です。お子さまの不登校に関して悩みごとがございましたら、お気軽に当院までご相談ください。