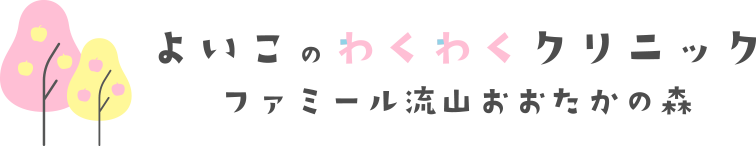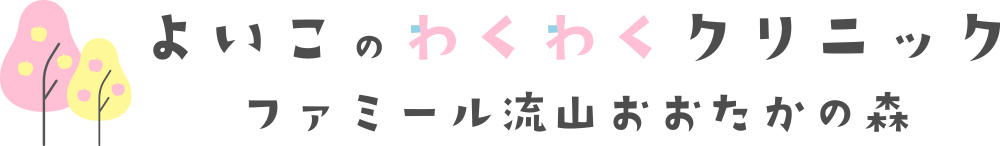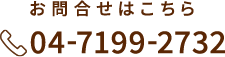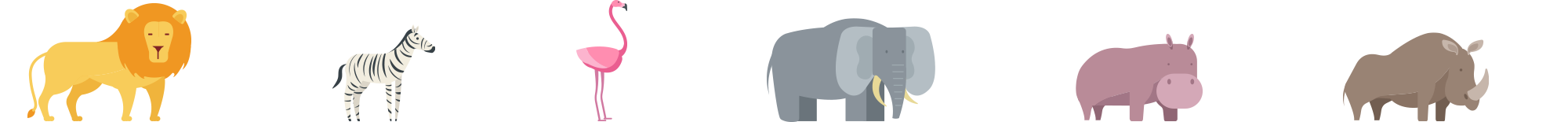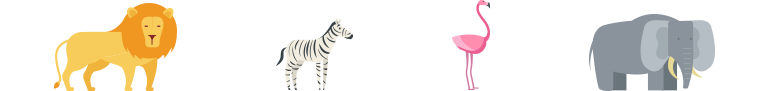子どもが頭を打ったらどうしたらいい?
お子さまが頭部をぶつけた場合、まずは冷静に状況を確認し、意識や呼吸、反応に異常がないか注意深く観察してください。軽い打撲であっても、症状が現れるまでに時間がかかるため、しばらく安静にさせ様子を見ることが大切です。もし、ぐったりしたり、嘔吐、意識の低下、痙攣、息苦しそうな様子が見られる場合は、すぐに医療機関を受診してください。お子さまが安全に過ごせるよう、しっかりとケアしましょう。
受診してほしい子どもの頭部外傷の症状
頭部外傷の後、次のような症状が見られる場合は速やかに受診する必要があります。これらの症状は、脳内出血の可能性を示す大切なサインです。
受診すべき症状
- ぐったりしている
- 吐いている
- 意識がない、またはもうろうとしている
- けいれんを起こしている
- 息苦しそうにしている
- 赤ちゃんの場合、ミルクを飲む量が減っている
これらの症状が認められたら、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。
子どもが頭を打ちやすい?
お子さまは、発達段階でバランス感覚や運動能力がまだ十分に成熟していないため、転倒や衝突が起こりやすく、頭を打つリスクが高まります。家庭内でも家具の角や階段など、頭部をぶつける可能性のある場所があるため、日頃から安全対策を徹底することが大切です。保護者の注意と環境整備で、頭部外傷のリスクを大幅に減らすことができます。
- お子さまは、頭部が体全体に対して大きく重心が高い傾向があるため、バランスを崩しやすく転倒しやすいです。
- 身長が低いため、視線も下に向きやすく、周囲全体を把握する視野が大人より狭くなっています。
- 好奇心が旺盛で、目の前のものにすぐ興味を持つため、全体の状況を瞬時に判断したり、危険を予測する力がまだ十分に備わっていません。
- 位置感覚が完全に発達していないため、自分の体の動きやバランスをうまく制御できないことが多いです。
- さらに、腕力が弱いため、転んだ際に自分を守るための反応が遅れ、危険な状況から回避するのが難しいのです。
子どもの頭部外傷が起きた時の対応
頭を打った際は、まずお子さまの意識状態、呼吸、反応を確認し、安全な場所に移動させましょう。その後、患部が腫れている場合は冷たいタオルや氷嚢で軽く冷やし、痛みを和らげる対策を行います。ただし、打撲の様子が軽い場合でも、後から症状が現れることがあるため24時間は慎重に観察し、異常があれば速やかに医療機関を受診してください。
傷口の手当て
子どもが頭をぶつけて出血した場合、まずは傷口の清潔を保つことが大切です。水道水でやさしく洗い流し、石鹸で軽く洗浄してください。洗浄後は、滅菌ガーゼまたは清潔なタオルで約10分間、優しく圧迫して出血を止めます。もし、打撲により腫れが見られる場合は、タオルに包んだ氷を腫れた部分に当て、20分程度冷やすと効果的です。
休息をとる
外傷後は、お子さまが十分に休める環境を整えることが必要です。症状が落ち着くまでは、少なくとも2時間は横になって休ませましょう。眠そうな様子であれば無理に起こす必要はなく、保護者の目が届く場所で寝かせ、しっかりと様子を見守ってください。
食事・水分補給
 頭部外傷後は、まず水分補給を心がけましょう。1~2時間経っても吐き気が見られない場合、食事も徐々に摂らせて構いません。ただし、吐き気が続いているときは固形物を避け、無理に食べさせるのは控えましょう。お子さまが十分な栄養と水分を補給できるよう、様子を見ながら対応してください。
頭部外傷後は、まず水分補給を心がけましょう。1~2時間経っても吐き気が見られない場合、食事も徐々に摂らせて構いません。ただし、吐き気が続いているときは固形物を避け、無理に食べさせるのは控えましょう。お子さまが十分な栄養と水分を補給できるよう、様子を見ながら対応してください。
注意すべき点
外傷後は激しい運動や頭を振る、ぶつかるような行動は避けるようにしてください。また、車などの乗り物での長距離移動は体への負担が大きいため控え、また、長風呂は避け軽く洗う程度に留めると安心です。さらに、食事や水分の摂りすぎも体に負担をかけるので注意しましょう。
子どもの頭部外傷の予防
お子さまの頭部外傷を防ぐためには、家庭内や遊び場での安全対策が欠かせません。家具の角にプロテクターを装着する、階段には安全柵を設ける、遊び場では十分な監視を行うなど、事故を未然に防ぐ工夫が大切です。保護者が常にお子さまの行動を見守り、安全な環境づくりを心がけましょう。
生まれる前から5か月頃まで
- お子さまが生まれる前に、家庭内の安全点検を行いましょう。特に階段や風呂場など、転倒のリスクが高い場所がないかを確認し、必要な箇所は修理、柵の設置、または鍵をかけるなどして安全対策を講じます。
- お子さまの移動時には、保護者が必ず両手でしっかり抱えて運び、床より高い場所に置いたり寝かせたりする場合も、転倒事故にならないよう細心の注意が必要です。
- また、お子さまの発育に合わせた育児グッズの選定も大切なポイントです。
6か月から1歳頃まで
- この時期は、階段、玄関、庭などでの転落事故が増える時期です。歩き始めたばかりのお子さまは、段差や敷居につまずきやすく注意が必要です。
- 転倒しても外傷が深刻にならないよう、床にマットを敷くなど、環境を整備する対策が求められます。
- 自宅に階段がある場合、出入口に柵や手すりを設置し、スペースが限られている場合は滑り止めマットや壁面にラバー素材を取り付けるなど、安全性を高める工夫をしましょう。
1歳から4歳まで
- 風呂場では、滑りにくい環境を作るとともに、浴槽内に一人で入らせないよう注意し対策を行います。
- 階段の上り下り時は、必ず保護者が付き添い、手を繋いで安全を確認しましょう。
- この年代では、自転車の乗り降りも事故のリスクが高まります。足台付きの補助座席を使用するなど、お子さまの安全を第一に考えた対策を講じ、車両を止める際は必ず先に子どもを降ろすようにしましょう。
5歳以降
- 幼稚園、保育園、小学校などの施設や、スポーツ活動において、事故や怪我の発生が増えてきます。
- 各施設では安全対策や安全教育が実施されており、また保護者自身もお子さまに対して危険意識を持たせるための指導が求められます。
子どもの頭部外傷のよくある質問
子どもが頭を打った時は受診した方がよいですか?
はい。特に重篤な症状(ぐったり、嘔吐、意識障害、痙攣など)がある場合は、すぐに受診してください。
子どもが頭を打った後はどのくらい様子を見ればいいですか?
軽度の打撲でも、24時間以内に症状の変化がないかを注意深く観察し、異常が見られた場合は受診してください。
子どもが頭を強く打ちましたが、元気であれば受診しなくていいですか?
見た目が元気でも、脳内出血や脳震盪の可能性があるため24時間は注意深く観察を行ってください。重篤な症状が出た場合は必ず医師の診察を受ける必要があります。
頭をぶつけてからどれくらいで症状が現れますか?
通常、打撲直後から数時間以内に症状が現れ始め、24~48時間かけて症状がはっきりしてきます。
子どもが頭をぶつけた時は受診した方がよいですか?
はい。特に意識障害や異常な反応がある場合は、早急に医療機関を受診してください。
たんこぶは脳に影響がありますか?
たんこぶ自体は皮膚の打撲によるもので、通常は脳に直接の影響はありませんが、大きさや痛みが気になる場合は医師に相談することをおすすめします。