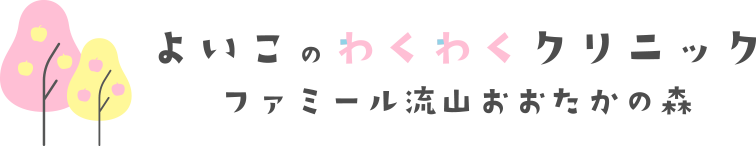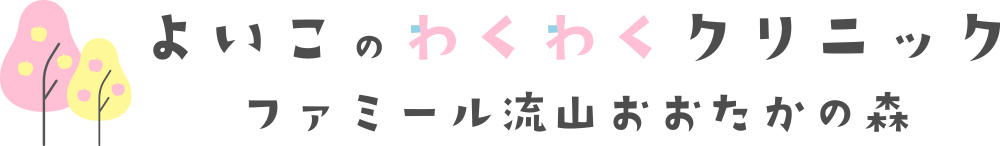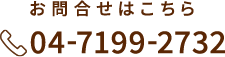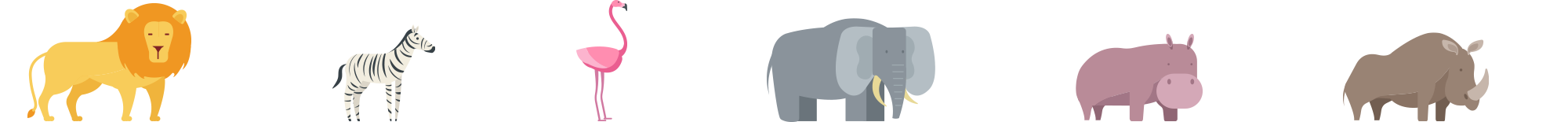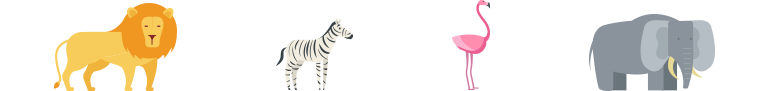公費での乳幼児健診について
公費での乳幼児健診は令和8年度から開始です。
乳幼児健診
 乳幼児健診は、成長過程にある乳幼児の健全な発育・発達を確認し、潜在的な健康問題や異常を早期に発見するための定期健診です。
乳幼児健診は、成長過程にある乳幼児の健全な発育・発達を確認し、潜在的な健康問題や異常を早期に発見するための定期健診です。
健診では、身体計測、発育や発達の評価、視力や聴力の簡単な確認、さらには生活習慣や栄養状態の確認などを行います。必要に応じて治療やお薬の処方も行います。
また、健診時には予防接種のスケジュール確認や、日常生活では気づきにくい症状の発見に努めることで、病気の早期治療や重症化予防を目指します。お子様の健やかな成長をサポートする大切な機会となります。
乳幼児健診を受ける目的
- お子さまの発育・発達の遅れや病気の早期発見、日常生活では気づきにくく、見逃しやすい異常の発見
- 予防接種の確認、病気や事故の予防
- 生活習慣の見直し・改善(離乳食の進め方、睡眠習慣などへのアドバイス)。
流山市の乳幼児健診について
| 実施時期 | 母子保健事業 |
|---|---|
| 生後3か月になる前日まで | 産婦・新生児訪問 |
| 2か月から4か月頃 | こんにちは赤ちゃん訪問 |
| 3か月から4か月まで | 3か月児健康診査(指定医療機関での個別健診) |
| 3か月から6か月まで | 乳児一般健康診査(指定医療機関での個別健診) |
| 4か月から5か月まで | もぐもぐ教室 離乳食教室前期(予約制) |
| 9か月から11か月まで | 乳児一般健康診査(指定医療機関での個別健診) |
| 11か月から12か月まで | カムカムキッズ 離乳食教室後期(予約制) |
| 1歳6か月から7か月まで | 1歳6か月児健康診査(指定医療機関での個別健診) |
| 2歳2か月から:3回コース | むし歯予防教室(申込み制) |
| 3歳3か月から4か月まで | 3歳児健康診査(保険センターでの集団健診) |
| 乳児・幼児 | 育児相談 |
| 予防接種法等に基づき実施 | 予防接種 |
乳幼児健診の流れ
乳幼児健診
2健診当日
来院
 予約日に来院・指定日時に来院します。
予約日に来院・指定日時に来院します。
当日の持ち物
- 予診票
- 母子手帳
- 健康保険証
- 乳幼児健康診査受診票(問診票):必要事項に記入して、ご持参ください。
- 乳幼児医療証・その他必要とされる医療証
などをお持ちください。
3問診・身体測定
身長・体重・頭囲・胸囲などを計測します。
4診察
 成長・発達上の問題がないか、身体所見の異常がないかなどを確認します。
成長・発達上の問題がないか、身体所見の異常がないかなどを確認します。
また、授乳や離乳食・睡眠などの生活面での疑問や、スキンケアの方法など、育児上のご不安や疑問があればお気軽にご相談ください。
5終了
健診後、受付で診察券や母子健康手帳などをお返しします。
なお、終了時には次回健診や予防接種のご予約も可能ですので、ご希望の方は受付にお伝えください。
乳幼児健診で気をつける症状・病気
3か月児健康診査
生後3か月頃の健診は、身体の成長や基本的な運動機能の発達を確認し、軽微な異常や体調不良の兆候を早期に発見することを目的としています。
気をつけるべき症状
- 体重の増えが悪い
- 筋緊張の低下
- 目が合わない
- 首がすわらない
- 不穏な泣き方・ぐずりが続く
発見できる病気
- 低栄養状態
- 発達障害の初期兆候
- 皮膚トラブル
乳幼児健康診査1回目(生後3か月-6か月)
生後3~6か月の期間における身体の成長や神経発達のチェック、睡眠・食事パターンの確認を行い、日常では見過ごしがちな異常の早期発見を目指します。
気をつけるべき症状
- 体重・身長の伸びが乏しい
- 首がすわらない
- 寝返りをしない
- 不規則な睡眠リズム
発見できる病気
- 栄養不足
- 発達障害の兆候
乳幼児健康診査2回目(生後9か月から11か月)
生後9~11か月の健診は、歩行や手先の発達、言語の始まりなど、次の発達段階に向けた基礎能力の確認と、成長曲線の推移を評価するために行われます。
気をつけるべき症状
- 身長・体重の伸びが乏しい
- 離乳食が進まない
- ハイハイやつかまり立ちの遅れ
- 手先の不器用さ
- 発語の遅れ
発見できる病気
- 運動発達障害
- 言語発達の遅れ
- 低身長・低体重
1歳6か月児健康診査
1歳6か月児健診では、歩行やコミュニケーション能力、食事や排泄などの生活習慣の発達状況を確認し、発育の遅れや障害の有無をチェックします。
気をつけるべき症状
- 身長・体重の伸びが乏しい
- 歩行や走行の不安定さ
- 発語が少ない
- 物の名前が理解できない
- コミュニケーションがとれない
発見できる病気
- 発達障害
- 栄養不良
- 運動機能の異常
3歳児健康診査
3歳児健診は、幼稚園入園前の発達段階の確認や、運動能力、言語能力、社会性など全体的な発達状況を把握し、集団生活に向けた健康状態を評価することを目的としています。
気をつけるべき症状
- 集団行動への適応の遅れ
- コミュニケーション不足
- 感情表現の乏しさ
発見できる病気
- 発達障害
- 自閉症スペクトラムの兆候
- 視覚・聴覚の異常
視力機能スクリーニング検査
乳幼児健診時には、年齢に応じた視力機能スクリーニング検査も実施されます。
この検査では、目の焦点合わせや視力の基礎的な反応をチェックし、斜視や弱視の早期発見を目指すものです。検査方法は遊び感覚を取り入れた簡単なもので、お子さまもリラックスして受けられるよう工夫されています。検査結果により、必要と判断された場合は専門の眼科受診をすすめ、早期の治療介入ができる体制が整えられています。
当院では新生児内科を専門としています
当院は新生児内科を専門とする院長が診療にあたっております。これまで、生まれたばかりの赤ちゃんや予定日より早く生まれたお子さま方の診療を担当してまいりました。その中で、お子さまだけでなくご家族の不安に寄り添い、最新の医療情報をもとに個々の症例に適した治療やフォローアップを実施してきました。
早産や低体重で出生したお子さまは、体格や発達にそれぞれの個性があり定期的な発達フォローが必要となります。また呼吸器感染症に罹りやすく、他児と比較して受診が必要となる機会が多いため、地域の中で安心してご相談いただける診療を行っていきます。
乳幼児健診のよくある質問
乳幼児健診は行かなくてもいいですか?
乳幼児健診はお子さまの成長や発達の状況を早期に把握する大切な機会です。行わない場合、発育の遅れや病気の初期兆候を見逃すリスクがありますので、ぜひ受診をおすすめします。
乳幼児健診は行かなかった場合はどうなりますか?
健診を受けないと、成長や発達の異常に早期対応できず、将来的に健康上の問題が拡大する可能性があります。定期的な健診は安心して育児を進めるために重要です。
乳幼児健診は保険適用になりますか?
基本的には、乳幼児健診は市区町村が実施しているため保険適用外となりますが、定期健診として公的に実施されているため、費用負担は軽減されます。
3歳児健診でまだおむつを使用している場合、尿検査はどうすればいいですか?
おむつ使用中の場合は、事前にご相談いただくか、必要に応じて別途尿検査の方法を調整いたします。
乳幼児健診で引っかかった場合はどうしたらいいですか?
異常が認められた場合は、詳しい検査や専門医への紹介、フォローアップを行います。保護者の方には丁寧に説明し、今後の対策をご提案いたします。
3歳児における発達障害のグレーゾーンの特徴は何ですか?
集団生活でのコミュニケーションの取り方や遊び方、言葉の発達の遅れ、興味の偏りなどが見られる場合、グレーゾーンとして評価されることがあります。詳細は専門医による総合評価が必要です。