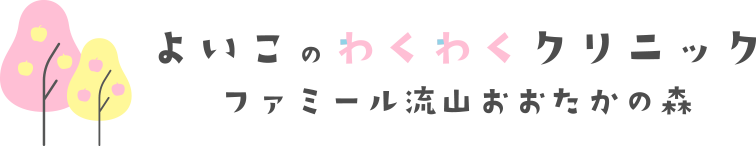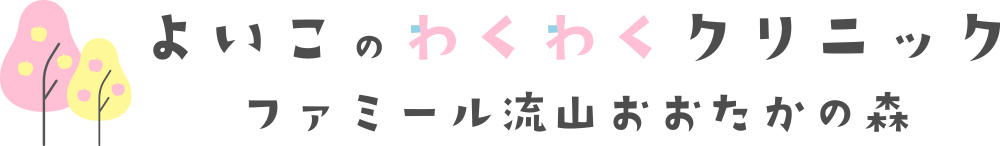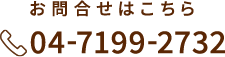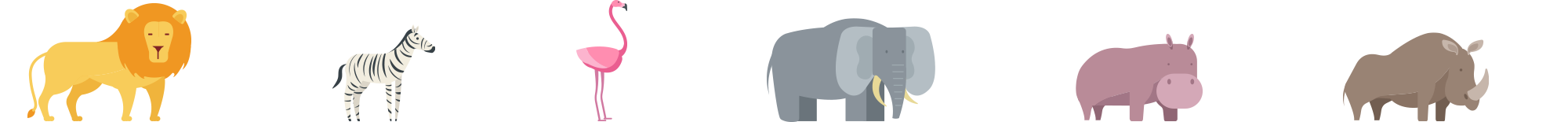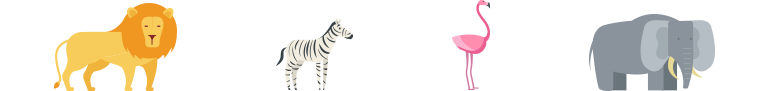おたふく風邪(流行性耳下腺炎)とは
 おたふく風邪(流行性耳下腺炎)は、ムンプスウイルスによる感染症で、主に小児に発症します。ウイルスが口や鼻から体内に侵入し、耳下腺や顎下腺、舌下腺などの唾液腺に感染することで、腫脹や痛みを引き起こします。初期には発熱や全身倦怠感が現れ、数日後に片側または両側の唾液腺が腫れるのが特徴です。感染後、自然回復することが多いものの、合併症のリスクもあるため、十分な休養と水分補給、医師の指導のもとで適切な管理が求められます。
おたふく風邪(流行性耳下腺炎)は、ムンプスウイルスによる感染症で、主に小児に発症します。ウイルスが口や鼻から体内に侵入し、耳下腺や顎下腺、舌下腺などの唾液腺に感染することで、腫脹や痛みを引き起こします。初期には発熱や全身倦怠感が現れ、数日後に片側または両側の唾液腺が腫れるのが特徴です。感染後、自然回復することが多いものの、合併症のリスクもあるため、十分な休養と水分補給、医師の指導のもとで適切な管理が求められます。
おたふく風邪の症状
おたふく風邪の主な症状は、ウイルス感染による全身症状と唾液腺の炎症が挙げられます。初期には微熱や倦怠感が現れ、数日後に唾液腺の腫脹と痛みが顕著になります。咽頭痛や頭痛、嚥下時の不快感も伴うことが多いです。症状の出現順や程度は個人差がありますが、以下の症状が一般的にみられます。
- 発熱
- 唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下線)の腫脹
- 唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下線)の痛み
- 頭痛
- 倦怠感
- 嚥下痛
など
おたふく風邪の原因
おたふく風邪は、ムンプスウイルスによる感染が原因です。ウイルスは飛沫感染や接触感染により広がり、感染者が咳やくしゃみをした際に放出されるウイルス粒子を吸引することで感染します。また、ウイルスが付着した物品を介して接触感染するケースも報告されています。感染後、ウイルスは主に唾液腺に集まり炎症を引き起こすため、腫脹や痛みなどの症状が現れます。感染経路や個人の免疫状態により症状の重さは変動し、合併症のリスクを高める要因となることもあります。
反復性耳下腺炎と流行性耳下腺炎は違う?
反復性耳下腺炎は、一度の流行性耳下腺炎とは異なり、同じ唾液腺の繰り返しの炎症を指します。流行性耳下腺炎は主にムンプスウイルスによる単発の感染症であり、通常は一度感染すると生涯免疫がつくとされています。一方、反復性耳下腺炎は、他の要因(例えば自己免疫反応や細菌感染など)によって引き起こされる場合があり、再発を繰り返すことが特徴です。両者は症状が似ている場合もありますが、原因や治療方針が異なるため、正確な診断が求められます。
おたふく風邪の合併症
難聴
おたふく風邪に伴う難聴は、ウイルスが内耳に影響を及ぼすことで発生することがあります。一時的な難聴の場合が多いですが、重度の場合は永続的な聴力低下につながることも報告されています。発症後、早期の治療と十分な休養が重要であり、聴力検査などによる経過観察が推奨されます。
無菌性髄膜炎
無菌性髄膜炎は、おたふく風邪の合併症として、ウイルスが髄膜に炎症を起こすことで発症します。細菌性髄膜炎と異なり、細菌は検出されないものの、高熱や頭痛、首の硬直などの症状が現れるため注意が必要です。多くの場合は自然治癒しますが、症状が重い場合は入院し、専門医による治療が必要となります。
脳炎
おたふく風邪による脳炎は、ウイルスが脳組織に侵入し炎症を引き起こすまれな合併症です。高熱、意識障害、痙攣などの神経症状が現れ、場合によっては後遺症を残すこともあります。迅速な診断と治療が必要であり、重症化リスクが高いため、発症が疑われた場合は直ちに医療機関を受診する必要があります。
脳症
脳症は、ウイルス感染に伴う脳機能の一過性または永続的な障害で、混乱、けいれん、意識障害などの症状が現れます。おたふく風邪による脳症は稀ですが、発症すると重篤な後遺症を残す可能性があるため、早期の診断と適切な治療が求められます。
精巣炎
精巣炎は、特に思春期以降の男性に見られる合併症で、ウイルスが精巣に影響を与え、腫脹や痛みを引き起こします。精巣炎が重度の場合、長期的な不妊リスクや精巣機能低下も懸念されるため、早期治療が重要です。症状が現れた場合は速やかに泌尿器科を受診し、適切な対処を行う必要があります。
卵巣炎
卵巣炎は、女性においてまれに見られる合併症で、ウイルスが卵巣に影響を及ぼし、下腹部痛や発熱を伴います。重症化すると卵巣機能に影響を及ぼす可能性があるため、早期の診断と治療が求められます。経過観察や必要に応じた画像検査などにより、適切な治療が実施されます。
おたふく風邪の検査
おたふく風邪の診断は、主に唾液腺の腫脹や痛み、発熱などの臨床症状と問診を基に行われます。症状が確認され、さらに合併症を認め診断確定が必要な場合には、血液検査やウイルス抗体検査を実施し、ムンプスウイルスの感染を確定します。場合によっては、PCR検査によりウイルスの遺伝子を検出し、より正確な診断を行うこともあります。検査結果に基づき、適切な対症療法や合併症の管理が行われます。
おたふく風邪の治療
対症療法
おたふく風邪の治療は、基本的には対症療法が中心となります。発熱や頭痛、筋肉痛などの症状に対しては、解熱鎮痛剤を用いて症状緩和を図ります。また、十分な休養と水分補給を徹底することが重要です。唾液腺の腫脹や痛みに対しては、口腔内のうがいや温湿布などの局所療法を併用し、症状の軽減に努めます。特効薬はないため、合併症の有無を確認しながら経過観察を行います。
合併症予防のためにも予防接種が大切!
おたふく風邪は合併症のリスクを伴う感染症ですが、ムンプスウイルスに対する予防接種により、発症リスクや重症化の可能性を大幅に低減できます。予防接種は接種後に免疫がつくため、流行期に備えて事前に受けることが推奨されます。また、集団生活を送る環境では、感染拡大防止の観点からも重要な対策となります。合併症予防と健康管理のため、定期的な予防接種の実施が大切です。
おたふく風邪のよくある質問
子どものおたふく風邪の初期症状は何ですか?
初期症状としては、軽い発熱、全身の倦怠感、食欲不振などが現れ、その後に片側または両側の耳下腺が腫れ始めることが一般的です。
子どもがおたふく風邪かかったらどうしたらいいですか?
まずは安静にさせ、十分な水分補給と休養を確保してください。症状が重い場合や合併症が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診してください。
おたふく風邪か判断するにはどうすればいいですか?
症状の経過や唾液腺の腫脹・痛み、発熱の有無などを確認し、必要があれば血液検査やウイルス抗体検査を追加して判断します。医師の診断が必要です。
おたふく風邪はいつから登園・登校できますか?
一般的には発症後5日以上経過し、症状が改善した後に登園・登校が可能とされていますが、詳細は医師の判断に従ってください。
おたふく風邪は腫れるタイミングが左右違うことはありますか?
はい、左右で腫れ方や腫脹の程度に差が出る場合もありますが、いずれもウイルス感染による正常な反応です。症状の経過を見守ることが大切です。
おたふく風邪は一度かかったら、生涯ならないですか?
一度感染すると免疫がつくため、通常は再感染はしません。ただし、免疫低下時には軽度の症状が現れる可能性もあるため、健康管理が重要です。