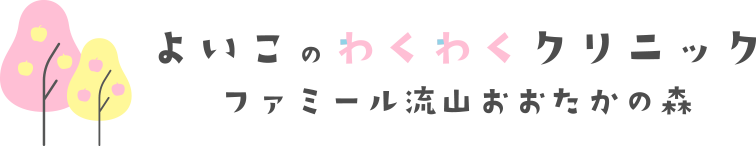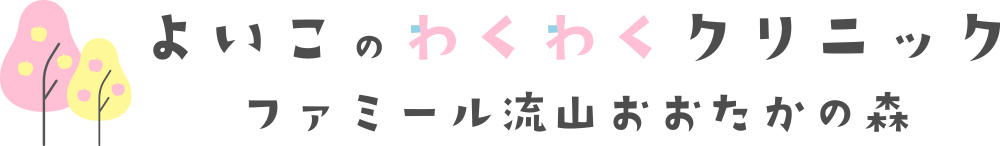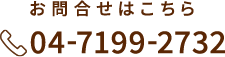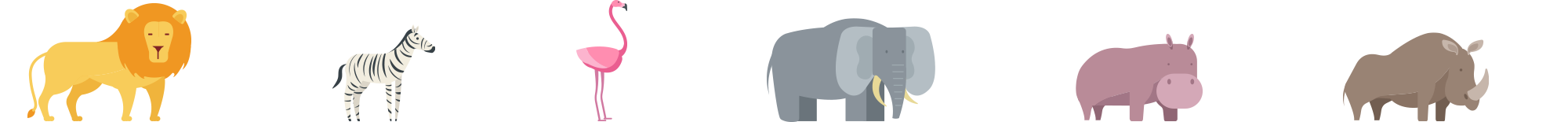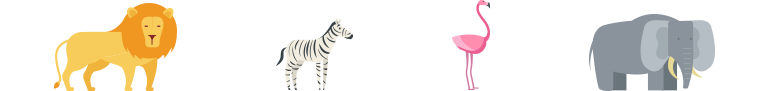何歳まで小児科を受診できる?
 小児科の対象年齢には明確な基準はありません。日本小児科学会では対象年齢を成人するまでと定めていますが、15歳からお薬の量が大人と同量になることから、一般的に15歳までを診療対象年齢としている医療機関が多く見られます。ただし、子どもの頃から喘息などのアレルギー疾患がある場合には、15歳を過ぎてもかかりつけの小児科で診療を継続することもあります。
小児科の対象年齢には明確な基準はありません。日本小児科学会では対象年齢を成人するまでと定めていますが、15歳からお薬の量が大人と同量になることから、一般的に15歳までを診療対象年齢としている医療機関が多く見られます。ただし、子どもの頃から喘息などのアレルギー疾患がある場合には、15歳を過ぎてもかかりつけの小児科で診療を継続することもあります。
子どもの体調不良は当院へご相談ください
お子さまが体調不良を起こした場合には、まずは小児科を受診することを推奨しています。子どもの症状の現れ方や症状の訴え方は大人と違って個性があるため、一般の内科や耳鼻科等では診断が難しい場合もあります。
何か気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。
親御様も同じ症状がある場合
同伴の親御様がお子さまと同じ症状がある場合は、お子さまと一緒に診察をお受けいただけます。保険証をご持参の上、受診予約をお願いいたします。なお、親御様が妊娠していらっしゃる場合や持病をお持ちで投薬を受けている場合は、かかりつけ医受診をお願いしています。
小児科と内科の違いは?
一般的に子どもの診療は小児科が、大人の診療は内科が行う医療機関が多く見られます。子どもは罹患しやすい病気や症状の現れ方が大人とは異なることが多く、自身の症状を大人のように上手に訴えることができません。また、子どもの場合には精神面や発達面に関する問題の質や特性も大人とは異なります。そのため、子どもに何か異常が起きた際には、経験豊富な小児科の医師に診断してもらう方が確実と言えます。
子どもの年齢によってかかりやすい病気がある?
乳児期早期
 生後3か月頃までの赤ちゃんは風邪を引いてもほとんど発熱を起こさないため、発熱の症状が見られた場合には、重症細菌感染症などの疑いがあります。
生後3か月頃までの赤ちゃんは風邪を引いてもほとんど発熱を起こさないため、発熱の症状が見られた場合には、重症細菌感染症などの疑いがあります。
乳児期
乳児期に入ると、食物アレルギーを訴える子どもが見られるようになります。お子さまに食物アレルギーを疑う症状が現れた場合には、自己判断で対応せずに当院までご相談ください。アレルゲンの可能性がある食品をむやみに避けたりすると、子どもの成長に支障をきたす恐れがあります。
乳児期・幼児期
乳児期~幼児期に入ると風邪を引いて発熱する子どもが多く見られるようになります。しかし、これは様々な種類の風邪ウイルスの免疫を獲得していく重要過程です。
一般的に子どもに多く見られる感染症には、インフルエンザや手足口病、RSウイルス、溶連菌、アデノウイルスなどが挙げられます。これらの中には発熱とともに熱性けいれんを併発するものもあります。
また、この時期になると喘息や花粉症、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患も見られるようになります。
学童期
学童期に入るとそれまでに多くの風邪ウイルスに対する免疫を獲得しているため、発熱を起こす頻度も徐々に低下していきます。その一方で、おねしょや低身長、肥満症、学習困難など、この時期特有の症状や問題が現れるようになります。
思春期
思春期に入ると、生活習慣の乱れや心理的な問題、二次性徴の異常、慢性頭痛、起立性調節障害などの自律神経症状といった複雑な症状や問題を訴えるお子さまが多く見られるようになります。