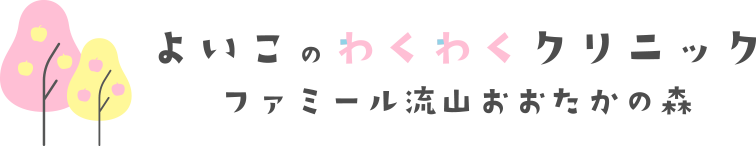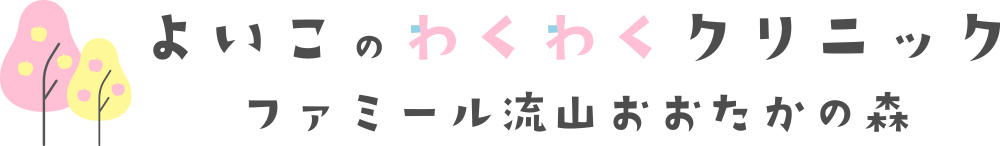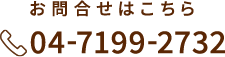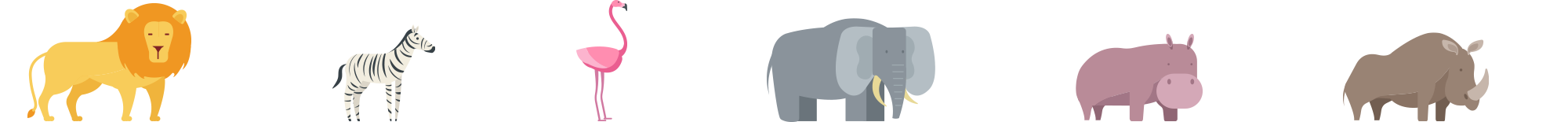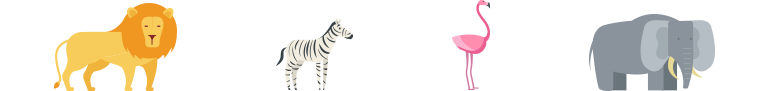流山おおたかの森近くの小児科
当院では、発熱や咳、鼻水、嘔吐、下痢、発疹などの急性疾患からアトピー性皮膚炎、気管支喘息などの慢性疾患まで幅広く小児科として診療を行っています。また、各種健診や予防接種の実施、お子さまの成長や子育てに関する相談についても承っております。より精密な検査や専門性の高度な治療が必要と判断した場合には、連携する高次医療機関をご紹介いたします。
何かお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ご家族さまへのお願い
お子さまを診療するにあたり、事前に以下の情報をお伝えいただけますと診察がスムーズに行えます。お答えできる範囲で構いませんのでご協力の程よろしくお願いします。
- 症状が始まった時期
- 食事・水分摂取の状態
- ご家族さまや周囲に類似した症状が現れているか
- お子さまの体重
- 現在服用中のお薬
- 過去の病気の罹患歴(いつ頃どんな病気にかかったか)
- アレルギーの有無
小児科のよくある症状
- 発熱を繰り返す
- 発熱とともにけいれんを起こす
- 咳が出る・長引いている
- 咳の際に嘔吐する
- 咳とともにヒューヒュー・ゼーゼーという喘鳴を伴う
- のどが痛い
- 鼻水・鼻づまりを起こす
- 頭がぼーっとする
- 頭痛が生じている
- 目が充血している
- 目やにが多く出る
- 便が出づらい
- 便が軟らかい
- 湿疹を繰り返す
- 肌の赤み、腫れ、痛み、かゆみ、乾燥、発疹、ジュクジュクしているなどの肌のトラブル
- デリケートゾーンのかゆみ
- 性器の赤み・腫れ・痛み、肌荒れなどの陰部のトラブル
- 顔色が悪い
- 吐き気や嘔吐を起こしている
- 食欲が減退している
- ぐずっていることが多い
- 最近頭を打った
- 最近階段から落ちた
など
発熱
 日本人の体温は36.6~37.2℃ですが、乳幼児は大人よりも平熱が高い傾向があります。また、体温は同日内で 1℃程前後すると言われています。主な原因は、単なる風邪の場合もあれば、他の病気の一症状として現れている場合もあります。そのため、発熱とともに他の症状を併発しているかどうかを確認することも診察する上で大切です。
日本人の体温は36.6~37.2℃ですが、乳幼児は大人よりも平熱が高い傾向があります。また、体温は同日内で 1℃程前後すると言われています。主な原因は、単なる風邪の場合もあれば、他の病気の一症状として現れている場合もあります。そのため、発熱とともに他の症状を併発しているかどうかを確認することも診察する上で大切です。
咳が出る
咳とは、外部から肺や気管支に侵入してきた異物を排除するための反応であるため、一過性の咳症状の場合は特に問題はありません。しかし、咳が1か月以上継続している場合には、何らかの病気やアレルギー症状の可能性があります。受診の際には過去に使用したお薬、現在の服用歴を把握するため、お薬手帳の持参をお願いします。
鼻づまり・鼻水
 鼻水の色が透明か白色で鼻水以外の症状を伴っていない場合は、特に問題はありませんので経過観察に留めます。しかし、黄色や緑色をした鼻水が慢性的に出ている場合は、副鼻腔炎や細菌感染症の疑いがあります。これらは放置すると重症化する恐れもあるため、気になる症状が現れている場合にはできるだけ早くご相談ください。
鼻水の色が透明か白色で鼻水以外の症状を伴っていない場合は、特に問題はありませんので経過観察に留めます。しかし、黄色や緑色をした鼻水が慢性的に出ている場合は、副鼻腔炎や細菌感染症の疑いがあります。これらは放置すると重症化する恐れもあるため、気になる症状が現れている場合にはできるだけ早くご相談ください。
のどの痛み
一般的に、のどの痛みは細菌やウイルスが咽頭や扁桃に感染して炎症を引き起こすことで発症します。
のどの痛みの原因には、風邪の他、急性咽頭炎や急性扁桃炎など様々な要因があるため、痛みが長引いている場合には医療機関を受診して詳しい状態を調べる必要があります。
頭痛
お子さまの頭痛の原因には発熱や自律神経の乱れ、片頭痛などがあります。頭痛の頻度が低い場合には一過性の症状の可能性もありますが、頭痛とともに鼻水や鼻づまりなどを併発している場合には、副鼻腔炎の疑いがあります。副鼻腔炎などの場合には抗生物質など薬の服用の必要がありますので、まずは原因を特定するため早めに医療機関を受診するようにしましょう。
便秘
10人に1人程の子どもが便秘であるという報告があります。一般的に排便が週3回以下であったり、5日以上排便がない場合には、便秘と診断します。また、毎日適切に排便が行われていても、排便時に痛みを伴ったり、肛門から出血が見られる場合も便秘と診断します。子どもの便秘は放置すると慢性化する恐れがあるため、上記のような症状が現れている場合には、医療機関を受診して適切な治療を行うことが大切です。
嘔吐
 嘔吐を起こした場合は、まず脱水症状を防ぐために少量ずつ水分補給を行いましょう。また、嘔吐を引き起こす原因を特定するために、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。特に、嘔吐とともに顔色が悪い、発熱や下痢を併発しているなどの症状が見られる場合には、自己 判断で放置せずに速やかに当院までご相談ください。
嘔吐を起こした場合は、まず脱水症状を防ぐために少量ずつ水分補給を行いましょう。また、嘔吐を引き起こす原因を特定するために、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。特に、嘔吐とともに顔色が悪い、発熱や下痢を併発しているなどの症状が見られる場合には、自己 判断で放置せずに速やかに当院までご相談ください。
原因が特定できた際には、症状に応じた内服薬や座薬を使用して改善を図ります。
腹痛
腹痛の原因は、便秘やウイルス性腸炎といった軽度のものから、盲腸や腸重積症、アレルギー性紫斑病など重度のものまで多岐に渡ります。そのため、激しい腹痛を起こしたり、症状が繰り返し現れていたりする場合は、できるだけ早く医療機関を受診して原因を特定する必要があります。
特に、腹痛とともに顔色が悪い、血便が出る、下痢や嘔吐を伴っているなどの症状を併発している場合は、早急に当院までご相談ください。
下痢
下痢の原因の多くはウイルス性の急性胃腸炎となります。急性胃腸炎は、ほとんどの場合5日程度で自然に改善しますが、食欲があるのに1日に5回以上の下痢が1週間以上継続している場合には何らかの病気の疑いがあります。速やかに当院までご相談ください。
普段の食習慣についてお伺いし、レントゲンや腹部エコー、血液検査などの検査が必要と判断した場合は、高次医療機関へご紹介します。
小児科のよくある病気
- 熱性けいれん
- 熱中症
- 風邪(風邪症候群)
- 気管支炎
- 扁桃炎
- 副鼻腔炎
- 百日咳
- クループ症候群(急性喉頭気管支炎)
- インフルエンザ
- 新型コロナウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- マイコプラズマ肺炎
- ノロウイルス
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- RS ウイルス
- 麻疹(はしか)
- 風疹
- ヘルパンギーナ・手足口病
- 低身長
など
熱性けいれん
熱性けいれんとは、一般的に生後6か月~5歳までの子どもが38℃以上の発熱を起こした際に起きるけいれん発作のことを言います。主な特徴には、けいれんとともに意識がなくなる、白目をむいてからだが硬くなる、手足が震えるなどが挙げられます。多くの場合は、5分程で自然に回復しますが、中には髄膜炎や急性脳症などの類似した症状を起こす別の病気の可能性もあります。5分以上経ってもけいれんが治まらない、いつものけいれんとは様子が違うなどございましたら、当院までご相談ください。
熱中症
熱中症とは、炎天下などに長時間滞在することで大量の汗をかき、からだの水分量や塩分量が低下した状態です。主な症状には、からだがぐったりする、けいれんを起こすなどが挙げられます。子どもは大人に比べて熱に対する抵抗力が弱いために 5月頃でも熱中症を起こす恐れがあり、注意が必要です。近年では春先から夏日になることも多いことから、親御さまは、お子さまの水分補給や塩分補給に気を配るようにしましょう。
風邪(風邪症候群)
風邪とは、正式には風邪症候群と呼ばれ、発熱やくしゃみ、鼻水、咳などの症状を引き起こす病気の総称です。主な原因は、ウイルスがのどや鼻の粘膜に感染して炎症を引き起こすためと考えられています。
ウイルスは細菌とは異なり特効薬がないため、治療では症状を抑えるための対症療法を行い、からだを安静に保ってウイルスが体外に排出されるのを待つことが基本となります。
気管支炎
気管支炎とは、細菌やマイコプラズマなどが気管支に感染して炎症を引き起こす病気です。特に、風邪などでからだの抵抗力が低下した際に発症しやすい傾向があります。多くの場合、炎症は咽頭や喉頭で起きますが、進行すると肺まで炎症が拡大して高熱や激しい咳症状を 伴う他、呼吸困難を引き起こす恐れもあります。
主な治療法は風邪と同等となりますが、赤ちゃんの場合は重症化しやすいため、入院治療によって抗生物質の投与などを行う必要があります。
扁桃炎
扁桃炎とは、左右に一つずつある扁桃腺が細菌やウイルスに感染することで炎症を起こす病気です。主な症状には、発熱やのどの痛み、頭痛、全身倦怠感、関節痛などが挙げられます。子どもに多く見られるのが溶連菌の感染による扁桃炎で、この場合は、抗生物質による治療を行う必要があります。なお、溶連菌への感染は大人でも起こすことがあるため、上記のような症状が継続している場合には医療機関を受診することをご検討ください。
副鼻腔炎
副鼻腔炎とは、鼻の奥に存在する副鼻腔が炎症を起こす病気です。主な症状には、鼻づまりや黄色・緑色で粘性の高い鼻水が多く出るなどが挙げられます。また、発熱や頭がぼーっとする、鼻がつまることで臭いを嗅ぎ取りにくくなる、鼻水がのどに流れることで咳症状を伴うなどの症状を併発することもあります。
主な治療は、副鼻腔内の細菌を排除して炎症を抑えたり、副鼻腔内の膿を排出させたりするなどの処置を行います。なお、副鼻腔炎は治療せずに放置すると病状が慢性化する慢性副鼻腔炎へと進行する恐れがあるため、注意が必要です。
百日咳
百日咳とは、百日咳菌に感染することで引き起こる病気です。主な症状には、ヒューヒューという喘鳴を伴う咳が多く出ることが挙げられます。新生児の場合はチアノーゼを引き起こし、入院治療が必要になることもあります。
治療では、マクロライド系抗生剤を7日から14日程使用します。生後1か月から3か月の児の発症が多いため、生後2か月から接種できる五種混合ワクチンを受けて発症を予防しましょう。また罹患しても治療後には再発を予防するために5種混合ワクチンを接種します。なお、大人の場合は百日咳とは気付かずに放置して感染を拡大させてしまうこともあるため、注意が必要です。
クループ症候群(急性喉頭気管支炎)
クループ症候群とは、細菌やウイルス感染によって喉頭部が炎症を起こし、特有の咳症状を伴う病気の総称です。流行時期は、原因となる細菌やウイルスによって様々なパターンがあります。特に秋~冬は、空気が乾燥することで罹患数が増加傾向にあります。
主な治療は、十分な水分補給や鎮咳去痰剤・気管支拡張剤・ステロイドの内服、エピネフリンの吸入などになります。ただし、病状が重度の場合には入院治療が必要になることもあります。
インフルエンザ
インフルエンザウイルスは例年冬から春先にかけて流行し、咳や鼻水などの風邪と似た症状の他、38℃以上の発熱や倦怠感、筋肉痛などを伴うことが特徴です。インフルエンザは、主に抗インフルエンザ薬やワクチン接種によって症状の改善や予防が可能ですが、インフルエンザウイルスは型が毎年異なるため、ワクチン接種も毎年行う必要があります。
新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症は、正式には COVID-19と言います。主な症状は発熱や腹痛、下痢、嘔吐などですが、基礎疾患がある子どもや2歳未満の子どもは重症化する恐れもあります。特に子どもは自身の症状を説明することが難しいため、親御さまが常に注意深く状態を確認することが大切です。
子どもの場合、新型コロナウイルスをはじめ、多くの感染症に罹患する恐れがあるため、気になる症状が現れた際には速やかに医療機関を受診するようにしましょう。
溶連菌感染症
 溶連菌感染症とは、溶連菌という細菌に感染することで発熱やのどの痛み、発疹などを引き起こす感染症です。A群、B群、C群、G群など様々な種類がありますが、症状が現れるのはほとんどが A群です。進行すると急性糸球体腎炎やリウマチ熱などの重篤な病気を合併する恐れもあり、注意が必要です。
溶連菌感染症とは、溶連菌という細菌に感染することで発熱やのどの痛み、発疹などを引き起こす感染症です。A群、B群、C群、G群など様々な種類がありますが、症状が現れるのはほとんどが A群です。進行すると急性糸球体腎炎やリウマチ熱などの重篤な病気を合併する恐れもあり、注意が必要です。
治療では、抗菌薬によって細菌を排除しつつ、発熱や発疹などの症状を緩和させるための対症療法を行います。
マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマは主に学校や家庭で感染が拡大する傾向があり、感染すると2~3週間の潜伏期間を経て、咳や発熱などの症状が現れます。進行すると肺炎や心筋炎、スティーヴンス・ジョンソン症候群、ギランバレー症候群、血球貪食症候群などの重篤な病気を合併する恐れもあり、注意が必要です。
主な治療は、マクロライド系やニューキノロン系、テトラサイクリン系の抗生物質になります。
ノロウイルス
ノロウイルスは、感染すると発熱や吐き気、腹痛、嘔吐、下痢などの食中毒の症状を引き起こす感染症です。1年通して感染の恐れがありますが、主に冬場に多く発生する傾向があります。便や吐物にウイルスが存在しているため、感染者がトイレ後に十分に手を洗わずに触れたトイレのドアノブなどを介して感染していきます。非常に感染力が強いため、家庭内感染を避けるために石けんを用いた手洗いをしっかり行うことが大切です。特に、子どもや高齢者が感染すると重篤化する恐れがあり、注意が必要です。治療は、症状を改善させるための対症療法を中心に行います。
咽頭結膜炎(プール熱)
咽頭結膜炎とは一般的にプール熱と呼ばれているもので、アデノウイルスに感染することで発症する感染症です。主な症状は発熱や目のかゆみ、充血、目やにが多く出る、扁桃炎などが挙げられます。症状は5~7日で自然に改善することが多いですが、中には重篤化して髄膜炎を合併することもあり、注意が必要です。
アデノウイルスは、年間を通して感染する恐れがありますが、一般的に夏場に感染することが多く、子どもの三大夏風邪の1つとも言われています。
主な治療は、発熱やのどの痛み、目の痛み、目の充血などの症状を改善させるための対症療法が中心となります。高熱が続く場合には脱水症状を引き起こす恐れもあるため、十分な水分補給を行うことも大切です。
RSウイルス
RS ウイルスとは感染すると発熱や鼻水、痰が絡む咳などを引き起こす感染症で、2歳までの子どもの多くがかかる傾向があります。一般的に症状は数日~1週間程で自然に改善することが多いですが、新生児や1歳未満の乳児が感染すると細気管支炎や肺炎などの重篤な症状を合併する恐れもあり、入院治療が必要になる場合もあります。
麻疹(はしか)
麻疹とは、麻疹ウイルスに感染することで発症する感染症です。主な症状には、咳や鼻水、目の痛み、目の充血などの他、38℃以上の熱を繰り返す、からだに発疹が出るなどが挙げられます。進行すると、肺炎や脳炎などの重篤な病気を合併する恐れもあるため、気になる症状が現れた際は、できるだけ早く医療機関を受診して治療を行うようにしましょう。治療では、症状を改善させるための対症療法を実施します。
風疹
風疹とは、風疹ウイルスに感染することで発症する感染症で、症状が軽度の麻疹のような特徴があることから三日はしかとも呼ばれます。風疹ウイルスに感染すると、2~3週間程の潜伏期間を経てから発熱や鼻水、咳、発疹などの症状が現れます。一般的に発熱や発疹は、3~4日程で自然に改善します。
治療では、症状を緩和させるための対症療法を実施します。多くは数日で改善しますが、中には症状が長引いて入院治療が必要になることもあります。なお、風疹は、風疹麻疹ワクチン(MRワクチン)を接種することで予防することが可能です。
ヘルパンギーナ
ヘルパンギーナとは、エンテロウイルスに感染することで発熱や下痢、口内炎などの症状を引き起こす感染症です。また、病状が進行すると、心筋炎や髄膜炎などの重篤な病気を合併する恐れもあります。
ヘルパンギーナと手足口病の違いとしては、ヘルパンギーナは口だけに痛みなどの症状が出るのに対して、手足口病では手や足など口以外にも発疹などの症状が出ます。また、基本的な治療方法などは大きく違いはありません。
手足口病
手足口病とは、コクサッキーウイルスやエンテロウイルスなどに感染することで発症する感染症です。一般的に夏場に感染が拡大することが多く、感染すると 38℃以上の発熱の他、のどの奥に多数の口内炎ができる、手のひらや足底、さらにお尻などにも発疹が現れるといった症状を引き起こします。発疹は水疱疹ですが、体幹には認めにくいことが水ぼうそうとちがいます。
手足口病の原因となるウイルスは複数の型があるため、別の型のウイルスにより再感染を起こし、手足口病を何回も発症することがあります。
低身長
一般的に子どもの身長は両親からの遺伝の要素が強いと言われていますが、成長ホルモンの分泌が不十分な場合や、骨・染色体の異常によって身長が伸びないこともあります。お子さまの身長が同世代の友達と比較して低い場合や、身長が伸びるペースが遅い場合には何らかの病気が関与している可能性があるため、一度当院までご相談ください。
治療では、主に身長を伸ばすための成長ホルモンの投与を実施しますが、この治療を行うには専門病院で行われる検査結果が一定の基準を満たす必要があります。お子さまの成長の経過をみて、必要があれば高次医療機関へご紹介します。
新生児内科について
 生後4週間以内の新生児でも発熱や咳、鼻水、鼻づまり、嘔吐、湿疹、あせもなどの症状を起こすことがあります。この時期は毎日のようにからだが発達するとともに、乳幼児や小児と異なる特徴も多いことから、診療には専門的な知識や経験が要求されます。
生後4週間以内の新生児でも発熱や咳、鼻水、鼻づまり、嘔吐、湿疹、あせもなどの症状を起こすことがあります。この時期は毎日のようにからだが発達するとともに、乳幼児や小児と異なる特徴も多いことから、診療には専門的な知識や経験が要求されます。
当院では、経験豊富な小児科専門医・新生児専門医である医師が新生児の診療を担当します。子どもに気になる症状が現れたり、子育てにお悩みがあったりする場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
新生児のよくある症状
- 鼻づまりを起こしている
- 呼吸が荒くなることがある
- 1回の哺乳に30分以上かかる
- よく嘔吐する
- 口の中が白い
- 目やにが多く出る
- 逆さまつげ
- 耳の臭いがきつい
- しゃっくりが多い
- いきむ、うなることが多い
- 2~3日に1回しか排便しない
- 排便の回数が多い
- 皮膚の色が黄ばんでいる
- 顔や腕にアザがある
- 臍が出ている(でべそ)
- 精巣の大きさが左右で違う
- 股関節が硬い
- 足首が両方とも内向き(内反)である
- 膝や股関節を動かすとポキポキ音がする
など
乳幼児健診の実施もしています!
当院では乳幼児健診を実施しています。乳幼児の時期は日々からだが発達するとともに、この時期特有の症状を起こすこともあるため、健診によって子どもの状態を正確に把握しておくことは大切です。
なお、各乳幼児健診には対象期間が設定されているため、事前に市町村からの連絡をご確認ください。
※定期乳幼児健診は令和8年度から開始予定です。