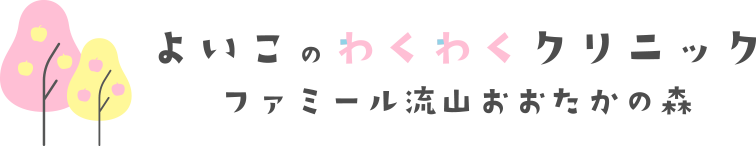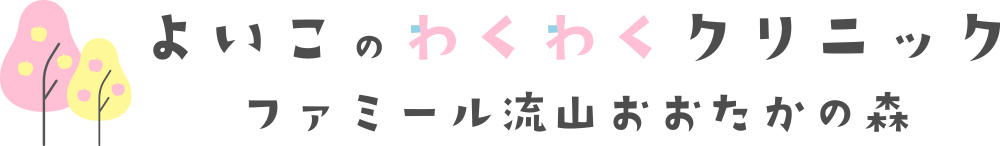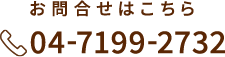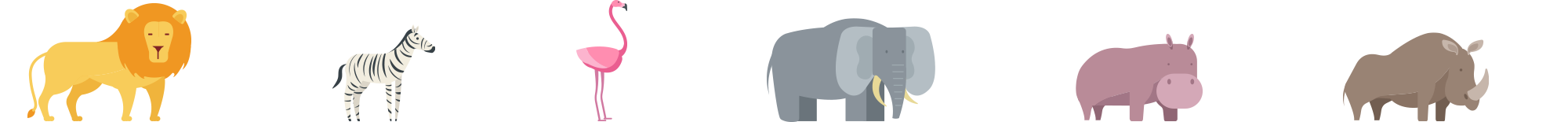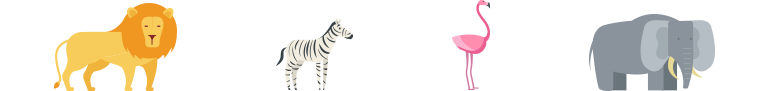子どもの低身長
 低身長とは、平均身長から標準偏差が2倍以上低い状態と定義されており、日本では2.3%が該当します。身長には個人差があり遺伝的要素も関与するため、低身長でも健康であれば特に問題はありません。しかし、中には何らかの病気によって成長障害を起こしていることもあります。
低身長とは、平均身長から標準偏差が2倍以上低い状態と定義されており、日本では2.3%が該当します。身長には個人差があり遺伝的要素も関与するため、低身長でも健康であれば特に問題はありません。しかし、中には何らかの病気によって成長障害を起こしていることもあります。
からだは、主に成長ホルモンなどの成長因子によって成長します。思春期に身長の伸びが著しいのは、成長ホルモンの一つである性ホルモンの影響を受けるためです。しかし、何らかの病気によって成長ホルモンの分泌が阻害されると、本来伸びるはずの身長まで到達せずに成長が止まってしまう成長障害を引き起こします。成長障害を起こすと、同世代の子どもと同等の能力が発揮できないなどの理由で自信を損失したり、劣等感によって精神面の成長にも支障をきたす恐れがあります。
現在では、成長障害に対して様々な治療法が確立されておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽に当院までご相談ください。
低身長の原因
子どもの身長の伸びが阻害されている状態を成長障害と言います。成長障害を引き起こす原因には、成長ホルモンの異常や染色体の異常、その他からだの器官の異常など様々な要因があります。
成長障害を起こす主な原因は以下となります。
ホルモン異常
身長の伸びに関与するホルモンには、成長ホルモンや甲状腺ホルモンがあり、これらのホルモン分泌に異常が生じると身長の伸びが悪くなることがあります。分娩の時に重症仮死になった場合や脳腫瘍などで成長ホルモンを分泌する下垂体が障害を受けると、成長ホルモンの分泌が阻害されて低身長を引き起こします。また、中にはこのような明確な病気が関与していなくても、軽度の成長ホルモン分泌不全によって身長の伸びが悪くなることもあります。その他、何らかの原因により成長段階で甲状腺ホルモンの分泌が不足し、身長の伸びの低下を招くことがあります。
身長の伸びが低下している原因がホルモン不足である場合には、不足しているホルモンを補充する治療の適応となります。
染色体の病気
ターナー症候群
ターナー症候群とは、2千人に1人の割合で女性に起きる染色体の異常で、2本あるX染色体のうち1本が欠損を起こした状態の病気です。主な症状には、身長の伸びが低下して低身長になったり、卵巣の発育を阻害して思春期になっても月経が見られなかったりするなどが挙げられます。また、難聴や心臓病などを合併することもあります。
対処法としては、低身長の場合は成長ホルモンを補う治療を行い、卵巣異常の場合には女性ホルモンを補う治療を行います。
プラダー・ウィリー症候群
プラダー・ウィリー症候群とは、1万人に1人の割合で起きる染色体の異常で、何らかの原因によって15番染色体が変化し、乳幼児期の筋力の低下が特徴的とされており、肥満や発達障害、低身長、性腺の発育異常などを引き起こす病気です。
成長ホルモンの補充療法を行うことで、筋力やからだの代謝、低身長などを改善することができます。
ヌーナン症候群
ヌーナン症候群とは、1万人に1人の割合で起きる先天的な遺伝子異常の病気で、発症すると低身長や思春期が遅くなるなどの症状の他に、特徴的な顔貌や心臓・血管の異常などを引き起こします。低身長を改善するためには、成長ホルモンの補充療法が適用されます。
子宮内発育不全
子宮内発育不全とは、胎児が子宮内で十分に発育できずに、一般的な新生児よりも身長や体重が小さな状態で生まれてくる状態の病気です。一般的に早産の場合によく見られますが、稀に妊娠満期であっても起こることがあります。
子宮内発育不全によって小さく生まれてきた子どもの多くは、3歳までに一般的なサイズまで追いつきますが、3歳を超えても身長が伸び悩んでいる場合には、成長ホルモンの補充療法を検討します。
骨や軟骨の病気
先天的な遺伝子の異常によって、からだの成長に関わる骨や軟骨が十分に発達せず、低身長や手足が短い、指が短いなどの特徴がみられる病気を軟骨無形成症と言います。多くは遺伝ではなく、軟骨無形成症ではないご両親から生まれてきます。
身体的な特徴から生まれてすぐに気が付かれることが多く、高次医療機関での検査、診断を経て成長ホルモン補充療法や骨延長術などが行われます。
臓器の異常
心臓や肝臓、消化器などの臓器は、からだの成長に必要な様々な働きを担っているため、病気などによってこれらの臓器の機能が低下すると、低身長を引き起こすことがあります。中には、低身長である原因を特定するための検査によって、これら臓器の異常が発見されることもあります。
原因疾患に合わせた治療を行い、臓器の機能が回復すれば低身長も改善します。小児慢性腎不全によって腎機能や身長が規定値を満たしていない場合には、腎臓の治療とともに成長ホルモンの補充療法を行います。専門的な治療が必要な場合には、連携する高次医療機関をご紹介いたします。
その他の要因
低身長は遺伝や体質、栄養、睡眠、運動といった基本的要因の他にも、ホルモン分泌異常や慢性的な病気、お薬の副作用に伴うもの、愛情不足やストレスといった心理的要因など様々な要因が複合的に重なって生じると考えられています。また、一般的に男性では声変わり、女性では月経が開始すると、その後の身長の伸び率は低下していくため、お子さまの低身長に関してご心配な場合は早めのご相談をお勧めします。
低身長の検査
まずは問診や身長・体重の計測、診察を行います。精密検査の必要性がある場合は専門病院に紹介しその後スクリーニング検査である一次検査へと進みます。一次検査では、血液検査や胸部レントゲン検査、甲状腺機能検査、染色体検査などを実施します。
一次検査で成長ホルモンの分泌異常を起こしている可能性が示唆された場合には、二次検査として成長ホルモン分泌試験を実施します。
低身長の治療
 低身長の治療は、主に原因疾患の改善と成長ホルモンの補充の2種類に大別されます。低身長を引き起こしている病気が特定されている場合には、その病気を治療することで低身長を改善できます。一方、成長ホルモン分泌不全やターナー症候群、プラダー・ウイリー症候群、軟骨無形成症などの場合には、成長ホルモンの補充療法を行うことで低身長を改善することができます。
低身長の治療は、主に原因疾患の改善と成長ホルモンの補充の2種類に大別されます。低身長を引き起こしている病気が特定されている場合には、その病気を治療することで低身長を改善できます。一方、成長ホルモン分泌不全やターナー症候群、プラダー・ウイリー症候群、軟骨無形成症などの場合には、成長ホルモンの補充療法を行うことで低身長を改善することができます。
成長ホルモンの補充をしても効果が出ない疾患として、多くの骨疾患、成長ホルモン受容体異常症、体質性低身長があります。骨疾患、成長ホルモン受容体異常症に関してはそれぞれ別の治療法で対応できますが、体質性低身長といわれる低身長に関しては病気ではないため治療法はありません。
生活習慣の見直しも大切!
身長の伸びは、食事習慣や睡眠、運動習慣といった生活習慣によっても変化します。栄養バランスの偏った食事習慣や睡眠不足、運動不足などの乱れた生活習慣を送っていると、身長の伸びを阻害し、低身長を引き起こすと考えられています。
低身長のよくある質問
成長ホルモンの補充注射以外に効果的な治療法はありますか?
成長ホルモン注射以外の治療法としては、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動が基本となります。また、腎臓や心臓などの内分泌系の異常が関与している場合は、それらの治療を併行して行うことが重要です。
成長ホルモンの補充注射をしたらどのくらいで効果が現れますか?
成長ホルモン注射は即効性があるわけではなく、からだに備わった成長能力を引き出す治療になります。効果が実感されやすいのは、注射を始めてから1~2年後と言われています。治療は継続することが大切です。気になることがございましたらお気軽にご相談ください。
身長は遺伝によって決まりますか?
身長は遺伝の影響を強く受けますが、他にも成長ホルモンの分泌異常、染色体異常、骨の病気などが原因で低身長になる場合もあります。環境や健康状態も影響するため、成長に異常を感じた場合は、医療機関に受診することをおすすめします。
子どもの低身長にいち早く気づくには何をすれば良いですか?
お子さまの成長を定期的に記録し、乳幼児健診や学校での身体測定を活用して成長の変化を確認することが大切です。標準的な成長曲線から外れていないかをチェックし、不安があればお気軽に当院へご相談ください。
低身長にはどのような悪影響がありますか?
健康に大きな影響はありませんが、社会的な価値観によって劣等感を持つことがあるかもしれません。1人1人の個性として向き合いながら、過ごすことが一番大切です。また、心臓や腎臓の疾患が原因の場合、適切な治療を受けないと病気が進行する恐れがありますので、低身長でお悩みや不安がある場合は、お気軽に当院へご相談ください。
低身長でなくても成長ホルモンの補充注射を希望することは可能ですか?
成長ホルモン注射は、ホルモン分泌が不足している場合や、特定の基準(−2.5SD以下の低身長)を満たす場合にのみ適用されます。適用基準は血液検査や成長ホルモン分泌負荷試験で判断します。治療が適用されるかどうかを確認したい場合は、一度当院へご相談ください。