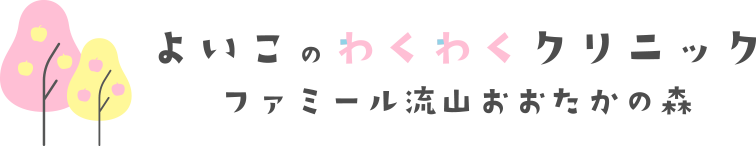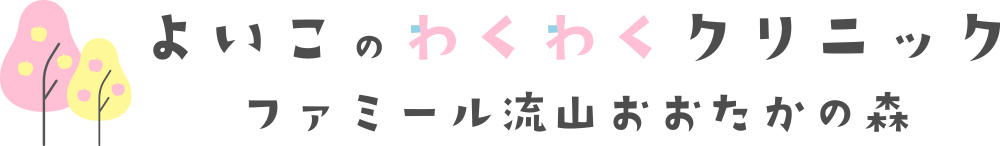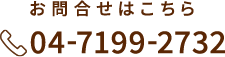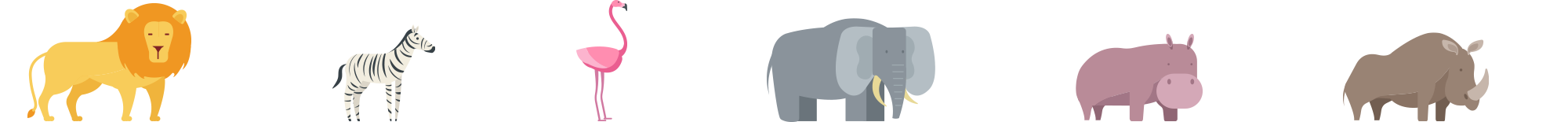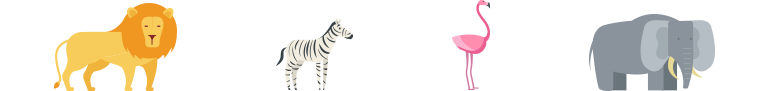子どもの泌尿器の病気
 泌尿器とは、尿が生成されてから排出されるまでの一連の流れに関わる臓器の総称です。泌尿器の対象範囲は、尿を生成する腎臓や尿をためる膀胱、尿を膀胱まで運ぶ尿管や尿道などになります。また、男性の場合は精巣と陰茎、女性の場合は膣と子宮といった性器も泌尿器に含まれます。
泌尿器とは、尿が生成されてから排出されるまでの一連の流れに関わる臓器の総称です。泌尿器の対象範囲は、尿を生成する腎臓や尿をためる膀胱、尿を膀胱まで運ぶ尿管や尿道などになります。また、男性の場合は精巣と陰茎、女性の場合は膣と子宮といった性器も泌尿器に含まれます。
当院では、夜尿症や頻尿、性器のトラブルなど、お子さまが引き起こしがちな様々な泌尿器疾患の診療を行っております。お子さまに気になる症状が現れた際には、どうぞお気軽にご相談ください。
子どもの泌尿器でよくある病気
尿路感染症
尿路感染症とは、腎臓で尿が生成されてから尿管、膀胱、尿道を通じて体外に排出されるまでの通り道に細菌が感染し、炎症を起こす病気です。主な原因菌は大腸菌ですが、中には腎尿路奇形が原因で発症することもあります。
尿路感染症の主な症状には、発熱や下腹部の違和感、腰背部痛、頻尿、排尿痛などが挙げられます。放置して病状が進行すると、入院治療が必要になる場合もあるため、気になる症状が現れている場合は、速やかに医療機関を受診して尿検査を受けるようにしましょう。特に乳児は、言葉で身体の異変を訴えることができないため、乳児が感染した場合には周囲がいち早く異変に気付いてあげることが大切です。
なお、入院治療が必要と判断した場合には、連携する高次医療機関をご紹介いたします。
膀胱炎
膀胱炎とは、何らかの原因によって膀胱が炎症を起こす病気で、原因のほとんどは細菌の感染になります。膀胱は尿を蓄積・排出する役割を担っている器官であるため、膀胱炎を発症すると排尿痛や頻尿、残尿感などの様々な排尿障害を引き起こします。
排尿時に痛みや違和感が生じた際には、できるだけ早く当院までご相談ください。
血尿・尿蛋白
血尿や蛋白尿とは、尿に血液やタンパク質が混入している状態で、これらは他の病気の一症状として現れる場合が多く、急性および慢性糸球体腎炎、膠原病、IgA腎症、ネフローゼ症候群などの腎臓疾患が考えられます。
当院では血液検査と尿検査を行います。腎疾患の疑いがある場合は腹部超音波などの専門性の高い検査および治療ができる高次医療機関へご紹介いたします。
膀胱尿管逆流症
膀胱尿管逆流症とは、膀胱にたまった尿が尿管、腎臓に逆流を起こす病気です。主な症状は尿路感染症に伴う症状で、高熱や脇腹痛、排尿痛、頻尿などが挙げられます。お子様が小さい時期には高熱のほかに下痢や嘔吐、不機嫌といった非特異的な症状がでることもあります。鼻水や咳などの症状がないのに、何回も高熱を繰り返す場合は尿に異常がないかを確認する必要があります。尿路感染症以外の症状では、年長児の日中の尿漏れや学校検尿の異常などで発見されることもあります。
放置すると腎機能低下に伴う腎不全に陥ることがあり、早期発見・早期治療が重要なため、気になる症状が現れている場合には速やかに医療機関を受診するようにしましょう。なお、より専門性の高い治療が必要と判断した場合には、連携する高次医療機関をご紹介いたします。
神経因性膀胱
神経因性膀胱とは、何らかの原因によって排尿に関わる神経に障害が起きることで、膀胱の機能が低下する病気です。主な症状は排尿困難や頻尿、尿漏れ、残尿感などですが、進行すると腎機能低下などを引き起こす恐れもあるため、早期発見・早期治療が重要です。
尿失禁(オムツがとれない)
 尿失禁とは、尿意を我慢できずに漏らしてしまう排尿障害の一つです。主な原因は、膀胱や尿道の機能やこれらに関わる神経の異常などが考えられています。放置すると尿路感染症や腎機能低下などを引き起こす恐れもあるため、早期治療が望ましいとされます。ただし、5歳までの子どもによる夜間のおねしょに関しては特に問題はないため、治療の必要はありません。
尿失禁とは、尿意を我慢できずに漏らしてしまう排尿障害の一つです。主な原因は、膀胱や尿道の機能やこれらに関わる神経の異常などが考えられています。放置すると尿路感染症や腎機能低下などを引き起こす恐れもあるため、早期治療が望ましいとされます。ただし、5歳までの子どもによる夜間のおねしょに関しては特に問題はないため、治療の必要はありません。
夜尿症(おねしょ)
おねしょ(夜尿症)は「5歳以上で1カ月に1回以上の頻度で夜寝ている間のおもらしが3カ月以上つづくもの」と定義されます。7歳児における夜尿症の有病率は 10%程度とされ、夜尿症の児はその後年間 15%ずつ自然に治るとされますが、0.5~数%は夜尿が解消しないまま成人に移行するといわれています。
生活指導をはじめとする治療介入により自然経過に比べて治癒率を2~3倍高めることができ、治癒までの期間が短縮するといわれています。
夜尿症はご家庭での育て方や子供の性格の問題では起こるわけではありません。夜尿症児への対処3原則は「あせらず」「おこらず」「起こさず」です。治療に際してはお子様ご本人の治したいという意志とご家族のサポートが大切になります。
夜間多尿タイプ
一晩の尿量が多く、膀胱容量は充分ある場合。主な原因は、水分・塩分の過剰摂取や過度なストレスの蓄積、抗利尿ホルモンの分泌不足などが考えられています。これらによって夜間の尿の量が日中より多くなり、おねしょを誘発します。
排尿未熟タイプ
夜間の尿量は少なく、濃縮力は正常だが膀胱容量が少ない場合。主な原因は、膀胱をはじめとした排尿器官が未発達なことが考えられます。また、このタイプは夜間多尿タイプと異なり、おねしょだけでなく頻尿や昼間のお漏らしも起こすことがあります。
混合タイプ
夜間多尿タイプと排尿未熟タイプの両者が併発している状態です。夜尿症の治療としてはまず生活指導や行動療法を開始し、効果が乏しい場合には抗利尿ホルモン剤投与または夜尿アラーム療法を追加します。生活指導及び行動療法としては、就寝前にトイレに行くことや、夕食から就寝までの水分を制限するなどがあります。
抗利尿ホルモン剤は夜間尿量を減少させる効果のある薬剤で、就寝前に使用します。水中毒を防ぐために就寝前2~3時間以内の水分制限が必要となります。
また、膀胱容量を減らす原因として重要なのが便秘です。便秘の症状がある場合は併せて治療を行います。
真性包茎
包茎とは、慢性的に亀頭に包皮がかぶさっている状態のことを指します。通常であれば包皮は成長とともに自然と剥けてきますが、中には包皮が被ったまま成人以降まで成長する場合もあります。成人になり普段は包茎でも皮を下げると亀頭が出る仮性包茎の場合は問題ありませんが、完全に被ったままの真性包茎の場合は治療が必要となります。
真性包茎は、放置すると亀頭に汚れが溜まる、臭いがきつくなる、排尿障害を起こすなどの他、亀頭の皮膚が硬化することで尿道が閉塞し、炎症を起こす閉塞性乾燥性亀頭炎などの病気を併発する恐れもあります。
なお、包皮が剥けた後に元に戻らなくなって亀頭が腫れる嵌頓包茎を引き起こしている場合には、早急に治療が必要となります。専門性の高い治療が必要と判断した場合には、連携する高次医療機関をご紹介いたします。
亀頭包皮炎
亀頭包皮炎とは、包皮と亀頭の間に細菌が侵入することで様々な症状を引き起こす感染症です。一般的に、おむつ・パンツの蒸れやお風呂での洗浄不足、汚れた手で直接触るなどの行為によって細菌が増殖することで発症します。
主な症状は、排尿痛や亀頭・包皮が赤く腫れる、膿が出るなどで、重症化すると陰茎部全体が腫れて充血を起こすようになります。抗生物質の内服薬や外用薬を使用して細菌を排除する薬物療法を行います。