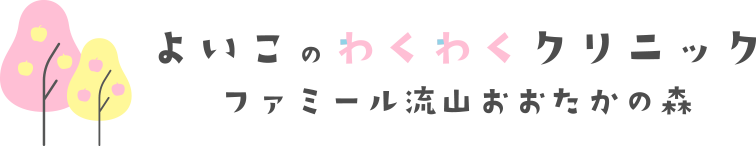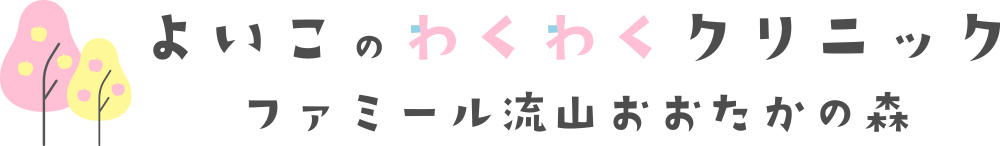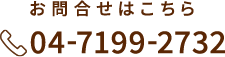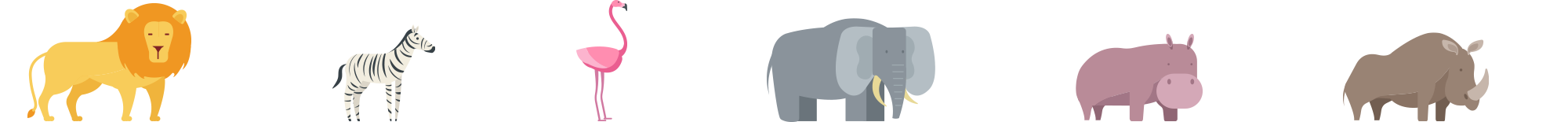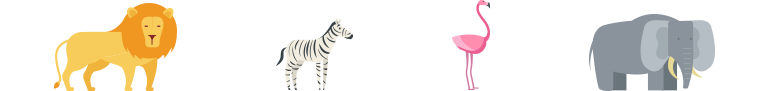定期予防接種について
定期予防接種に関しては令和8年度から開始です。
子どもの予防接種
 子どもの予防接種は、感染症を未然に防ぎ、集団全体の罹患率を下げる重要な取り組みです。厚生労働省によると、ワクチンを接種することで重症化を防ぎ、合併症のリスクを減らす効果が期待されます。特に乳幼児期は免疫機能が未熟なため、適切な時期に接種を進めることで、はしかや肺炎など重篤な病気を防ぐことができます。さらに予防接種には、接種者本人だけでなく、周囲への感染拡大を防ぐ「集団免疫」の役割もあります。こうしたメリットを踏まえ、決められたスケジュールに沿って接種を進めることが大切です。
子どもの予防接種は、感染症を未然に防ぎ、集団全体の罹患率を下げる重要な取り組みです。厚生労働省によると、ワクチンを接種することで重症化を防ぎ、合併症のリスクを減らす効果が期待されます。特に乳幼児期は免疫機能が未熟なため、適切な時期に接種を進めることで、はしかや肺炎など重篤な病気を防ぐことができます。さらに予防接種には、接種者本人だけでなく、周囲への感染拡大を防ぐ「集団免疫」の役割もあります。こうしたメリットを踏まえ、決められたスケジュールに沿って接種を進めることが大切です。
ワクチンの種類
ワクチンは、病原体そのもの、またはその一部を弱毒化・無毒化し、体内に投与することで免疫系を刺激し、将来同じ病原体が侵入した際に素早く抗体を作れるようにするものです。これにより発症や重症化を抑える効果が期待できます。
生ワクチン
生ワクチンは、病原体を弱毒化した状態で接種するため、比較的長期にわたる免疫が得られやすい特徴があります。一方で、免疫力が低い方への接種には注意が必要です。
不活化ワクチン
不活化ワクチンは、病原体を完全に殺して毒性をなくしたものを接種します。生ワクチンに比べて副反応が少ない一方、複数回の接種で免疫を高める必要があります。
トキソイド
トキソイドは、細菌が産生する毒素を無毒化・弱毒化して作られたワクチンです。ジフテリアや破傷風ワクチンが代表例で、毒素による発症や重症化を防ぐ役割があります。
予防接種の種類
定期予防接種
厚生労働省が実施を推奨する定期予防接種は、公費負担により原則無料で受けられる制度です。対象年齢や接種回数が法律や省令で定められており、適切な時期に受けることで感染症の流行を予防し、社会全体の健康を守る目的があります。代表的なワクチンには、ヒブ(Hib)や小児用肺炎球菌、B型肝炎、五種混合などが含まれます。接種スケジュールは必ず事前にご確認ください。
- Hibワクチン(インフルエンザ菌b型)
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- B型肝炎ワクチン
- 五種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)
- 四種混合ワクチン(DPT-IPV)
- ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ
- BCG(結核)
- 麻しん風しん混合ワクチン(MR)
- 水痘(みずぼうそう)ワクチン
- 日本脳炎ワクチン
- 二種混合ワクチン(DT)
- ジフテリア・破傷風(小学校高学年~中学生の追加接種)
- 子宮頸がんワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン)
小学6年生相当~高校1年生相当の女子
2022年4月より積極的勧奨が再開されています - ロタウイルスワクチン
2020年10月より定期接種化
任意予防接種
任意予防接種は、定期予防接種とは異なり法律上の接種義務はありませんが、感染予防や重症化の防止に有効とされています。代表的なものとしてはおたふくかぜ(ムンプス)ワクチンやインフルエンザワクチンなどが挙げられます。接種は自己負担となりますが、集団生活やご家族内での感染リスクを考えると、必要に応じて受けることが勧められています。実施時期や回数はワクチンごとに異なるため、ご相談ください。
任意予防接種(自費)
インフルエンザ予防接種(お子様と同時に両親の接種も可能です)
おたふくかぜワクチン
以下のワクチンは当院で行っていません
- 新型コロナワクチン
- 三種混合ワクチン(DPT)
- A型肝炎ワクチン
- RSウイルス母子免疫ワクチン(アブリスボ筋注用)
- シナジスやベイフォータスなどRSウイルスワクチン
- 不活化ポリオワクチン
- 狂犬病ワクチン
- 破傷風ワクチン
- 髄膜炎菌ワクチン
当院で対応している予防接種
以下に挙げるワクチンはすべて厚生労働省や国立感染症研究所が推奨する方法で接種を行っております。接種スケジュールや接種回数は、お子さまの体調や年齢によって異なりますので、必ず医師にご相談ください。
Hibワクチン(ヒブワクチン)
Hib(インフルエンザ菌b型)は、髄膜炎や肺炎、敗血症などを引き起こす細菌です。ヒブワクチンを接種することで、Hibに感染するリスクを大幅に減らすことができます。特に髄膜炎を発症した場合は死亡したり後遺症を残したりする可能性が高く、早期の予防が重要です。生後2か月から接種可能で、1回目を生後何か月で接種したかにより合計の接種回数が異なります。
2024年4月から四種混合ワクチンとヒブワクチンを混合した五種混合ワクチンが導入されました。2024年2月以降に生まれたお子さまは五種混合ワクチンを接種します。2024年3月までにヒブワクチンを接種している場合は、残りの必要回数も原則としてヒブワクチンを接種します。お子さまの予防接種記録を確認しながら、スケジュールに沿った接種をおすすめします。
肺炎球菌ワクチン(小児用)
肺炎球菌は集団生活をするほとんどのお子さまが保有しているといわれ、菌を持っていても無症状で過ごしているお子さまも多くいます。肺炎球菌に感染すると中耳炎や副鼻腔炎、肺炎、髄膜炎などの全身感染症を引き起こします。肺炎球菌による髄膜炎はHibによる髄膜炎と同様に乳幼児期にかかりやすく、死亡したり後遺症を残したりする可能性があります。生後6か月以降で肺炎球菌よる髄膜炎の発症数が増加するため、それまでに十分な免疫をつけておく必要があります。
ヒブワクチンと同様に生後2か月から定期接種として始められ、複数回の接種が推奨されています。1回目を生後何か月で接種したかにより合計の接種回数が異なります。
使用するワクチンの種類には20価ワクチンと15価ワクチンの2種類があり、2024年10月以降は原則として20価ワクチン(PCV20)を使用します。15価ワクチンで接種を開始したお子さまは、原則として15価ワクチンで接種を行います。
四種混合ワクチン(DPT-IPV)
四種混合ワクチン(DPT-IPV)はジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、不活化ポリオ(IPV)を予防する混合ワクチンです。それぞれの病原体から体を守るために、別々で接種する手間が減り、スケジュール管理が簡単になるメリットがあります。厚生労働省の承認を得たワクチンであり、生後2か月から接種が可能です。
2024年4月から四種混合ワクチンとヒブワクチンを組み合わせた五種混合ワクチンが新たに導入されました。2024年2月以降に生まれたお子さまは基本的に五種混合ワクチンを接種します。2024年3月までに四種混合ワクチンを接種していたら、残りの必要回数も原則として四種混合ワクチンを接種します。
これらの混合ワクチンを適切に受けることで、髄膜炎や百日せきなど重症化リスクがある感染症を効率的に予防できます。体調不良などで接種スケジュールがずれそうな場合は、早めにご相談ください。なお、五種混合ワクチンにはゴービックとクイントバックの2種類がありますが、2種類を区別せずに接種する交互接種はできません。
ロタウイルスワクチン
ロタウイルスは、乳幼児期(0~6歳ころ)にかかる胃腸炎の主な原因ウイルスで、乳幼児がこのウイルスに感染すると激しい症状が出ることが多いです。主な症状は嘔吐、水様便、発熱、腹痛です。脱水がひどい場合は点滴などの処置が必要となり、入院が必要となるケースもあります。
ロタウイルスワクチンには2種類あります。ロタリックスは単価のワクチンで2回接種、ロタテックは5価のワクチンで3回接種と違いがありますが、効果はほぼ同等とされています。初回はいずれも生後14週6日までに接種し、2回目、3回目も同じワクチンでなければいけません。
BCGワクチン
BCGは、結核予防のために接種する生ワクチンです。結核は肺を中心に感染を起こし、まれに重症化すると乳幼児では髄膜炎など深刻な合併症につながる場合があります。BCGワクチンは生後5~8か月までを対象とした定期接種として厚生労働省が推奨しており、接種部位に針痕が残る特徴があります。結核は減少傾向にあるものの、集団生活や地域差によっては依然としてリスクが存在します。後々の健康を守るためにも、対象月齢に合わせて接種を受けることをおすすめします。(参考:厚生労働省「定期接種実施要領」)
MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)
MRワクチンは、麻しん(はしか)と風しんの予防に用いられる生ワクチンです。麻しんは発熱や発疹を引き起こし、高熱や肺炎、脳炎などの合併症を伴いやすい疾患です。風しんは成人がかかると重症化することもあり、妊娠中の女性が感染すると胎児に先天性風しん症候群を引き起こすリスクがあります。MRワクチンを計2回受けることで、これらの病気を効果的に予防できます。厚生労働省では1歳と小学校入学前の年齢を接種対象としており、忘れずに受けることが大切です。(参考:国立感染症研究所「麻しん・風しん情報」)
HPVワクチン
HPVワクチンはヒトパピローマウイルスによる感染を予防し、子宮頸がんやその前がん病変の発生リスクを低減する目的で接種するワクチンです。厚生労働省では小学6年生から高校1年生相当の女子に対して定期接種を実施しています。HPVは将来的に子宮頸がんだけでなく、尖圭コンジローマなどの原因にもなるウイルスとされており、早期の接種によって予防効果を高めることが期待できます。副反応や接種後の体調変化などに不安がある場合は、必ず医師にご相談ください。(参考:厚生労働省)
水痘ワクチン
水痘(みずぼうそう)は、水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる感染症です。発熱および水ぶくれを伴う発疹が全身に広がり、まれに肺炎や脳炎を合併することがあります。
水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。
水痘ワクチンは生ワクチンとして1歳から接種でき、定期接種として2回の接種が基本です。1回の接種により重症化のリスクが大幅に下がり、2回の接種により軽症の水痘の発症をも予防できると考えられており、集団生活での流行を抑える効果も期待されます。
B型肝炎ワクチン
B型肝炎ウイルスによる肝炎発症を予防するワクチンです。感染すると急性肝炎を引き起こすだけでなく、慢性化して肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。厚生労働省では、2016年10月から定期接種化され、生後2か月以降に合計3回の接種を行うことが推奨されています。ワクチン3回接種後の感染防御効果は20年以上続くと考えられており、忘れずに接種を受けることが大切です。
おたふくかぜワクチン
おたふくかぜ(ムンプス)は、ムンプスウイルスによって唾液腺や中枢神経系などに炎症が起こる感染症です。主な症状は発熱、耳の下あたり(耳下腺)の腫れや痛みですが、髄膜炎や難聴、膵炎などの合併症を引き起こすことがあります。おたふくかぜワクチンは任意接種のため有料となりますが、感染リスクや合併症を考慮すると、接種により予防効果を得ることが重要です。特に保育園や幼稚園など集団生活を送るお子さまは、かかりつけ医と相談の上、1歳以降に接種を検討ください。(参考:国立感染症研究所)
おたふくかぜワクチンは2回の接種が推奨されており、1回の接種のみでは予防効果は十分ではありません。日本小児科学会では1回目を1歳になったら早めに、2回目を小学校入学前の1年間に接種することを推奨しています。
日本脳炎ワクチン
日本脳炎は、蚊を媒介とするウイルス感染症で、高熱や嘔吐で発症し、意識障害や麻痺などの神経の障害を引き起こし、後遺症を残したり死亡したりする病気です。
日本脳炎ワクチンは3歳から接種を開始することが標準とされていますが、0歳での発症報告もあるため、生後6か月からの接種開始が可能です。
国立感染症研究所によると、日本国内での大規模流行は減少していますが、海外旅行や蚊の発生状況などによりリスクがゼロになるわけではありません。安全に過ごすためにも、計画的な接種をおすすめします。(参考:国立感染症研究所)
二種混合ワクチン(DT)
二種混合ワクチンは、ジフテリア(D)と破傷風(T)の予防を目的としたトキソイドワクチンです。通常、小学校高学年(11~12歳)ごろに追加接種を行うことで、幼少期に受けた定期接種(DPT-IPVなど)の免疫効果を維持します。破傷風は傷口から菌が侵入し、その毒素により神経の働きが悪くなる感染症で、筋肉のこわばりや開口障害、呼吸困難などの症状が出ます。ジフテリアはジフテリア菌による感染症で、発熱や嘔吐、咳などから始まり、呼吸困難や嗄声などの症状がみられます。ジフテリア毒素により心筋障害や末梢神経麻痺などを発症リスクもあり、未接種の場合は注意が必要です。接種年齢やスケジュールは自治体によって異なることがありますのでご確認ください。(参考:厚生労働省)
インフルエンザワクチン
インフルエンザは毎年冬期に流行し、高熱や咳、倦怠感などの症状を引き起こすウイルス感染症です。ワクチン接種により発症を予防したり、かかった場合でも重症化を防いだりする効果が期待できます。小児は重症化リスクが高いため、医師の判断に基づいて年齢に応じた回数(通常2回)を接種することがおすすめです。インフルエンザウイルスは毎年変異しやすいため、厚生労働省は毎年の接種を推奨しています。幼稚園や学校など集団生活を送るお子さまは特にご検討ください。(参考:厚生労働省)
ご家族でインフルエンザワクチン接種が可能!
当院では、お子さまだけでなく保護者やご家族の方も一緒にインフルエンザワクチンを受けられます。
ご家族全員で予防接種を行うと、家庭内での感染伝播を大幅に抑える効果が期待されます。特に小さなお子さまがいるご家庭では、家族がウイルスを持ち込まないよう予防することが大切です。ご予約や費用に関してはお問い合わせいただき、そろって来院いただくとスムーズに接種できます。
予防接種スケジュール
当院では、厚生労働省や日本小児科学会の推奨するスケジュールに基づき接種を実施しています。下記もご参考ください。
予防接種に必要な持ち物
- 予防接種予診票(接種券)
- 母子手帳
- 健康保険証
- 「子ども医療」などの医療証
予防接種を受けられない場合はどんな時?
- 1週間以内に37.5℃以上の発熱があった方
- 定期接種の場合、接種券・予診票をお持ちでない方
- 医師の判断で接種ができないと診断された方
- 母子手帳をお持ちでない方
予防接種の副作用について
子どもの予防接種後は、注射部位の発赤、腫れや硬結(しこり)、発熱などの軽微な副反応が起こることがあります。通常、発熱は1日から2日で改善する場合がほとんどで、注射部位の発赤や腫れは数日でおさまりますが、硬結は数か月間残る方もいます。高熱が続いたり、発疹や呼吸困難など重い症状が現れた際は、速やかに当院にご連絡ください。
予防接種の費用について
定期予防接種は、公費負担により原則無料で受けることができます。一方、任意接種(おたふくかぜ、インフルエンザなど)は公的補助がないため有料となります。費用はワクチンの種類や接種回数によって異なるため、事前にお問い合わせください。
保護者が付き添えない場合
保護者の方が付き添えない場合は、委任状など必要書類をご用意いただき、別のご親族や代理の方が同行いただくことで接種可能です。各自治体や医療機関で書式や手続きが異なる場合がありますので、事前に当院までお問い合わせください。
子どもの予防接種でよくある質問
1番初めの子どもの予防接種は何ですか?
生後2か月から五種混合ワクチンや小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチンなどの接種が始まります。
予防接種で熱が出やすいものはありますか?
個人差がありますが、一般的に熱が出やすいワクチンとしては肺炎球菌や四種混合ワクチンなどが挙げられます。不活化ワクチン(肺炎球菌、四種・五種混合ワクチンなど)は当日から翌日に、生ワクチン(MR、水痘、おたふくかぜなど)は5-10日後に発熱することもあります。
予防接種後、保育園はいつから登園させていいですか。
副反応が落ち着いてからの登園が望ましいとされています。通常は翌日から問題ないことが多いですが、体調に応じて医師とご相談ください。
BCGワクチンの跡がつかない子どもはいますか。
個人差により跡が目立たない場合もあります。跡がつかなくても免疫はついていることがほとんどですが、気になる際は医師にご相談ください。
子どもに必ず接種しなければならない予防接種は何ですか?
法令で定められた定期予防接種(五種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、BCG、MR、水痘、日本脳炎、HPVなど)が該当します。
0歳へのインフルエンザワクチンの予防接種はできますか?
一般的に生後6か月未満の赤ちゃんは対象外とされるため、生後6か月を過ぎてから医師に相談のうえ接種するかを決めます。接種までに卵を食べさせたことがない場合や、卵を食べてアレルギー症状が出たことがある場合はインフルエンザワクチン接種が困難な場合があります。